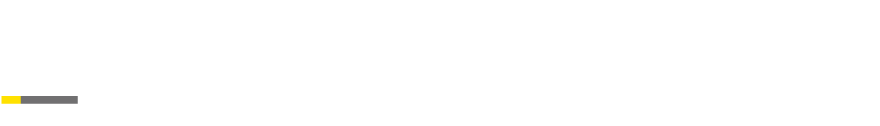
大学院理工学研究科 宮田竜彦講師が、当時理学部物理学科4回生であった村田将平さん、坂本萌さん、佐々木康さんとともにAIP advances(米国物理学協会(AIP))に発表した論文がEditor’s pickに選ばれました。
生物が生きていく上で、細胞内外でタンパク質が重要な働きをしているということは疑いようのないことでしょう。多くのタンパク質は、その機能を発揮する際に特定の構造をとる必要があります。非常に複雑なタンパク質分子がきれいに折り畳まる必要があるのですが、その構造は周囲の溶媒による影響を強く受けます。タンパク質分子周りにどのように溶媒分子が集まってきて、それがタンパク質分子とどのように相互作用するかが重要となります。これをタンパク質分子の「溶媒和」と言います。溶媒和の度合いを定量的に把握するときによく使われるのが、溶媒和自由エネルギー(*)と呼ばれる物理量です。コンピュータで溶媒和自由エネルギーを予測するときには純粋な溶媒だけの計算結果も必要となりますが、溶媒和自由エネルギーを正確に予測するためにはこの溶媒の計算も正確である必要があります。
生体内での現象に関与する溶媒は、水をはじめとした多原子分子であることがほとんどでしょう。本研究では最も単純な例として二原子分子からなる溶媒に焦点を絞り、その計算精度についてかなり徹底した調査を行いました。溶媒和自由エネルギー計算を念頭に置く場合は、溶媒の計算を分子動力学法(**)だけで行うのは難しく、RISM理論(***)という手法が使われます。RISM理論には複数の近似が含まれますが、本研究では特にclosure近似と呼ばれるものの影響に注目しました。closure近似として、HNC近似、KH近似、KGK近似に加え、これまで宮田講師のグループで開発されてきたSEB-KH近似(SEBという補正を施したKH近似)についても検討しました。
内部エネルギー、圧力、等温圧縮率という観点から各近似法の正確さを調べました。既存のclosureであるHNC、KH、KGKの中で言えば、KGK closure近似が最も正確であることが分かりました。つまり、熱力学的な観点ではRISM理論とKGK closure近似の相性がかなりよさそうだということです。またSEB補正法については、これまでLennard-Jones(LJ)ポテンシャルで相互作用する系にのみ適用されてきました。本研究では、LJとクーロンポテンシャルを重ね合わせたモデルへとSEB補正法が拡張され、その有効性が示されました。SEB-KH closure近似についても熱力学量が比較的正確であることが確認されました。
Accuracy of some useful closure relations in combination with the reference interaction site model theory for fluids of single component diatomic molecules
Tatsuhiko Miyata, Shohei Murata, Megumi Sakamoto, Yasushi Sasaki,
AIP advances, 12 (2022) 035248
(*) 溶媒和自由エネルギー
溶質(タンパク質分子など)を真空中から溶媒中へ移したときに、自由エネルギーがどれだけ変化したかを表す量。溶媒和自由エネルギーが低いほど、溶質は溶媒中で安定である。また溶媒和自由エネルギーが低いほど、その溶媒に溶けやすいという解釈もできる。
(**) 分子動力学法
物質内の各原子(または各分子)の運動を、運動方程式の数値解を用いて追跡していく方法。この方法は十分な計算量を確保できれば正確ではあるものの、多数の運動方程式を同時に解く必要があるために非常に大きな計算コストがかかる(十分な計算が行えない限り、正確にならない)。そのため、タンパク質などの計算を対象とすれば途端にスーパーコンピュータが必要となるが、それでも計算量が不十分である場合も少なくない。また、溶媒和の計算を念頭に置く場合は動径分布関数をかなり遠距離まで求める必要があるが、分子動力学法は遠距離の計算を苦手としている(ただし、近距離ではかなり正確に計算できる)。
(***) RISM理論
多原子分子からなる溶媒の数値計算を可能とする理論であり、分子動力学法と比べて計算コストがはるかに小さくて済む。一方で、理論に近似が含まれるため、結果の正確さには詳しい吟味と注意が必要である。RISM理論で見られる不正確さは単原子分子用のOrnstein-Zernike理論ともまた異なっており、その挙動の詳細な把握が望まれる。