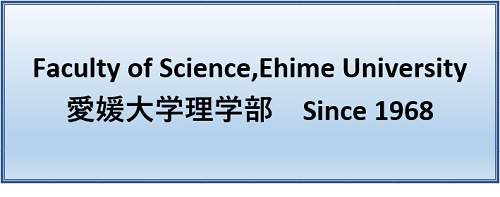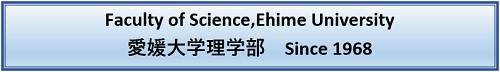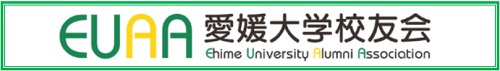母校の窓>2020
2020年度・2019年度末退職の先生方からのメッセージ
時間の単位
平出 耕一
10年ひと昔という表現をだいぶ前に聞いたことがあるが、ネットで調べてみると、5年をひと昔前と感じる人が一番多く、次いで3年で、10年をひと昔前と今でも考えている人の割合は3番目になっている。確かに5年は一つの区切りになりそうで、科研費の申請では、5年は最長の研究期間で、3年はほぼ最短になっている。理学部で以前発行していた「教育・研究のあゆみ」も5年ごとだった。しかし、この5年とか3年とかは、連続的に流れる時間の短い一つの単位だと思う。それに対し長めの時間の一つの単位として10年があるように感じる。このくらいになると物事は随分と変化する。大学に入学してから大学院を経て就職するのに大体10年かかったし、大学院での研究テーマに一つの終止符を打つのに更に10年くらいかかった。更に10年ほど研鑽を積んだが、このくらい経つと、辞書や本に引用されるようになってきて、国内外問わず世の中に知れ渡ってしまう。数学のような辛辣な学問は、頑張ったとしても、そのくらいの年齢で研究を止めるのが普通だと思っていた。今から30年ほど前、筑波大学から異動してきたが当時もそう思っていた。送別会のとき、少し大袈裟に、あと20年頑張りますと宣言した覚えがある。その時はそれほど本気ではなかったけれども、まさか逆に更に10年も追加されるとは夢にも思わなかった。そもそもその頃は、若手という明確な概念がなく、34歳までが少し優遇されていた時代で、科研費の申請も奨励研究というのがあって37才までで、それを過ぎると今でいう基盤研究で申請しないといけなかった。しかも研究期間は1年と定まっていた。ある意味、結構のんびりとした時代だった。その若手の頃、研究集会に参加するための交換条件で、北海道大学であった国立32大学の会議に出たことがある。情報交換の場だったが、メインが東京大学数理科学研究科の設置についての詳しい説明であったが、1人参加だったのでメモを取るのが大変だった。その内容は教室に持ち帰って少しは役に立ったと思うが、その頃から以降、全ての国立大学はものすごく大きく変わっていくことになり、15年くらい経過して、ついに法人化されてしまった。これは、丁度バブル経済の崩壊からリーマンショックの手前までの期間に起きたことで、その後もゆとり教育というのが続いていった。この様な中で、動き変化するのを止めると、倒れて消滅してしまうという仕掛けを組み込まれたような感じである。最近では、GとLによる大学間の差別化、年俸制導入など極まりを見せているが、これから先30年の間に何が起こるかは誰にも予測できないだろう。人工知能との関係でシンギュラリティを唱える人がいるが、それは今から30年後には既に起こっている出来事である。30年を時間の単位としてみると、社会環境はとてつもなく大きく変わったし、今後も変わるだろう。しかし、この30年で見ると、数学に対する研究態度がぶれることはなかった。そして、研究内容はどんどん発展している。研究対象も以前からの力学系の定性的研究を継続しつつ、今は加えて定量的研究も行い発展的に展開している。やはり、数学の研究の辛辣さは常套ではない。とても体力を必要とするし、それを持続しつつ、発展し続けなければならない。これは、数学の普遍性がもたらす必然だと思う。これからも真剣な態度で数学の研究を続けたい。
愛媛大学を去るに当たって
長岡 伸一
令和3年3月に大過なく定年退職を迎えることができました。これもひとえに在任中にお世話になった学部長をはじめ教員の皆様、職員の皆様、学生大学院生諸君、同窓会の皆様のおかげと心より御礼申し上げます。誠にありがとうございました。
私は、京都大学理学研究科を修了後、北海道大学応用電気研究所(現在は電子科学研究所)、岡崎国立研究機構(現在は自然科学研究機構)分子科学研究所を経て平成元年10月16日に愛媛大学理学部に転任して参りました。前任地の事務職員からは、転任日が中途半端な16日なので転任翌日の17日には月給が支給されず、11月17日に合算されて支給されるであろうと言われて転任して参りましたが、意外にも10月17日にきちんと給与が全額支給され、愛媛大学の事務組織がしっかり機能していることを思い知らされました。それ以来、退職に至るまで理学部職員の皆様にがっかりさせられたことはありません。誠にありがたいことでした。
理学部では、それまでに行ってきた化学反応の電子状態依存性の研究である励起状態での分子内プロトン移動反応や内殻励起によって分子内の特定の原子付近だけで起こる反応の研究に加えて、抗酸化反応の研究をさせていただきました。特定領域や重点領域の科研費が採択されて学生院生諸君とともに愛知県岡崎、茨城県つくば、兵庫県佐用のような日本のみならず、日米科学技術協力事業で米国にまで飛び回りましたので、留守中には他の教員の皆様には大変ご迷惑をお掛けしたと思います。誠に申し訳ありませんでした。いずれの研究でも、学生院生諸君は愛媛県唯一の国立大学の学生院生として、想定外のプライドを持って卒業研究や大学院の研究に取り組んでくれました。その成果は二百数十報の原著論文にまとめましたが、まだ報告できていない研究もあり、退職後もしばらくは論文のとりまとめを進めてまいります。
教育では、量子化学や構造化学の授業などを担当し、特にPCを用いた分子軌道法の演習という新しい教育手法に取り組みました。その成果は、アメリカ化学会の教育専門誌などに掲載されております。量子化学を充分理解することは数学が得意でない学生院生には難しいですが、単に講義を聴いて紙と鉛筆で演習をするだけではなく、普及しているマイクロソフト・エクセルを利用してデジタル的に「手を動かす」ことによって理解を促進しようと考え、このような実習を開発しました。原子分子の世界はとびとびなのに、さらに世間はとっくに連続なアナログからとびとびのデジタルに変化したのに、量子化学の教育が今もって連続を前提とした微分積分によって記述されるシュレーディンガー方程式に基づいているのは残念の限りであり、私の在職中にできるだけデジタルの世界に近づけるように教育手法を改良することを志してきましたが、数理統計や確率を用いた量子化学の教育手法を確立するまでに至らず中途にて退職することになりました。
社会貢献や運営では、日本化学会速報誌編集委員、分子構造総合討論会(現在、分子科学会)開催事務局、ビタミンE研究会開催代表世話人、環境機能科学専攻長などを拝命しましたが、力不足で余りお役に立てずに多くの先生方に負担が掛かったことをお詫び申し上げます。
北海道大学に初めて就職してからも、愛媛大学においても、様々な別の大学にお招きをいただきながら最終選考では不採用を繰り返していたにもかかわらず、愛媛大学理学部にお招きいただいてそのままずっと拾ったままでいただいたことに心より感謝いたしております。前任地から転任の折には、王昌齢の「洛陽の親友もし相問わば一片の氷心玉壺にあり」と唐詩選を引用しました(分子研レターズNo.23)。愛媛大学を去るに当たってどのような言葉を残したら良いのか迷っています。学生時代から「田舎の勉強よりも都の昼寝」と言われて教育されてきましたので、社会資本のより充実と大学環境のさらなる整備は期待したいところです。時代が変わっても大学教員に最後に残るのは研究成果でしょう。私は理学部研究奨励賞などいくつかの賞をいただいたとはいえ、会心の研究成果が乏しかったことは実力不足でお詫びする以外にありません。しかし、転任以来毎年友人たちが「松山詣で」と称してじっくりと研究を語り合うために訪ねてくれ、多くの論文にまとめられたのは良い思い出です。
最後に、多くの方々に支えられて退職を迎えることができたことに心より感謝を申し上げるとともにご迷惑をお掛けしたことをお詫び申し上げ、さらに黙々と尽くしてくれる妻にありがとうと言って愛媛大学を去るに当たっての言葉とさせていただきます。末筆になりましたが、愛媛大学理学部のさらなる発展と皆様のご活躍を念じております。ありがとうございました。
退職にあたって
大森 浩二
1983年4月に、フェリーに乗って、四国に上陸し、愛媛大学理学部に生物学科の助手として赴任しました。その頃の愛媛大学の大学祭で、正門の上に大きな瀬戸大橋の模型が飾られていたのを覚えています。開通したのはその5年後のことでした。大学院博士課程の途中から赴任したため、初めの数年は博士号取得のために九州天草(九州大学の臨海実験所所在地)へ通い、最後に国内留学をさせていただき、九大理学部から「干潟に生息するヨコエビの個体群動態論」により理学博士を頂きました。愛媛では、重信川河口の干潟で汽水性生物の研究を続けることとしました。この頃、宇和島の遊子漁協からの依頼で愛媛大学(工学部、農学部、理学部)のグループとして宇和島湾の養殖による有機物汚染の調査をはじめ、水域生態系の持つ生産と分解のバランスの最適解を見つけ、それを沿岸漁場生態系の健全性の指標とするとの研究を行いました。これらの研究がもとで持続的養殖生産確保法が作られ、施行されたのが1999年でした。前後してこの研究チームを中心として沿岸環境科学研究センターが、新設されそこの構成員となりました(理学部へ赴任してから16年目の年です)。一方、海洋調査に加えダム湖・湖沼生態系、東南アジアでの人工マングローブ林の機能解析の調査も始めました。この頃からベトナムへマングローブ林生態系の調査に行くようになり、ベトナム国ハノイ大学の学生を大学院への留学生として受け入れ、数名のベトナム人に理学博士の学位を取得させることができました。その後学部新設に関わり、2016年、また、新設の社会共創学部の環境デザイン学科へ移り現在にいたっています(16年周期で別組織へ放り出されている?)。
ここまで、現実の人間社会にどっぷりとつかった生態系の研究をつづけながら、生物進化科学、その中心的課題である種分化理論に20年前から取り組んでいます。
1858年出版のダーウィンの「種の起源」を土台としたネオダーウィニズムの、与えられた環境において、ランダムな変異から生まれた、高い適応度を示す遺伝子を持つ個体が生き残るという自然選択 (Natural Selection) 説が、現在、生物進化の原動力とされている。ただし、ダ―ウインの「種の起源」では、自然選択による新たな種の形成過程を説明できず、それ以来、100年にわたり、多くの議論がなされたが、1960年代にマイヤーが種の形成は、地理的隔離による種個体群の分断化(=allopatric speciation)によるものが主とし、それが定説となった。ところが、過去5年間に全ゲノム解析が多くなされるようになってきて、共通の祖先種から分岐したと思われる2種の各ゲノムのうち、適応的形質の遺伝子群が先に分岐し、のちに、分岐する二つの個体群間の遺伝子交流の減少に伴い、中立的な遺伝子群が分岐する例が普通に見られた。これは、地理的な隔離なし(= sympatric)、または、隔離が弱い(= parapatric)場合における種分化が普通に起こっていることを示しています。
祖先種から新たな種への変異が生じる種分化のごく初期の段階で、既存の種分化モデルは、新たに形成される種が占有する新たなニッチェへのほぼ完全な選好性のアプリオリな遺伝子変異(=かなり無理があると考えられる)を暗黙の裡に仮定している。しかし、この「ほぼ完全な選好性」という前提が崩れると地理的隔離なし、または、弱い場合の種分化が成立しなくなることが私の種分化モデル解析から証明できている。全ゲノム解析の研究結果から、地理的な隔離なし、または、隔離が弱い条件下における種分化が普通に起こっているとすると、分岐のごく初期の段階において、(まだ構成されていないが、後の段階において構成されるであろう新しいニッチェへの)ニッチェ選好性遺伝子(群)を介さない、生物の主体的な認知能力(=ある基準(拡張された適応度の最適化と考えられる)により自らが選択される環境(= selection field)を選ぶこと:ただし、認知能力そのものはNatural Selection により進化した適応的な能力と考えられる)による新たなニッチェへの選好性、つまり、自律選択(Autonomous Selection)を考えざるを得ない、という結論に達したところで退職の年となる2019年の年度末を迎えたわけです。時間切れです。ただ、2022年3月まで、特命教授として現在所属の社会共創学部へ残ることとなっていますので、その間、この地上で最も高い(自律選択に必要な)認知能力をもつと自負する我々ホモサピエンスの、ホモハイデルベルゲンシスからホモサピエンスへの最後の種分化を題材とした、分析哲学や量子力学で唱えられた自由意志定理に基づく種分化理論の論文を発表していきたいと考えています。
38年間本当にお世話になりました。ありがとうございました。
愛媛大学理学部で過ごした日々と自然災害
森 寛志
私は1994年4月に理学部地球科学科に赴任して以来26年間という長い時間を充実して楽しく過ごし、こうして無事に定年を迎えられたのはこれまでに理学部で出会い、共に過ごした多くの皆様のお陰だと感謝しております。本当にありがとうございました。
理学部ですごした26年間を振り返るにあたって、私が地球科学に関わっていたこともあり、この間に起こった自然災害、中でも地震被害を目の当たりにした時に感じたことや考えたことを述べていきたいと思います。
私が前任地の東京から松山に赴任した次の年、1995年1月17日に阪神淡路大震災が発生しました。地震発生は早朝午前5時46分で、私が当時住んでいた東温市にある愛大横河原宿舎の3階でも地震の揺れに驚いて目を覚ましたのを覚えています。神戸という大勢の人が暮らす大都市を最大震度7の大地震が襲ったのは衝撃でした。阪神高速3号神戸線の橋脚が横倒しになった光景がテレビに映し出され、この地震の揺れがいかにすさまじいものだったかを物語っていました。神戸市長田区などの住宅密集地で発生した大規模な火災の被害も甚大でした。大都市でひとたび大地震が発生すると6000名を超えるような大勢の尊い命が一瞬で失われることを学びました。地震の被害の大きかった場所は、地震断層に沿った比較的狭い範囲に集中して長く伸びており、やはり神戸市の海岸に沿った埋め立て地などのいわゆる地盤の弱い場所でより被害が大きかったようです。これは地表に暮らす我々にとって地震の揺れの大きさを決める要因として地震そのものの規模以上に揺れに対する地盤の強弱がいかに重要であるかを改めて印象付けることになりました。
2001年3月24日の15時28分に芸予地震が発生しました。震源地は安芸灘で、震源の深さは50kmでした。松山市の震度は、震度5強と記録されています。この日は土曜日で、私は東温市の自宅の庭にいましたが、まわりの樹木や家屋がユサユサと揺れ始め、とても驚きました。私がこれまでに自身で直接経験した地震の揺れの中では最大のものでした。翌週の月曜日に大学に向かうと研究室のロッカーの扉が皆半開きになっており、まるで泥棒に荒らされたようになっていたのには驚きました。幸い家具が倒れたり、棚の中身が散乱したりというようなことはありませんでした。しかし、理学部本館の壁面のあちこちにX字のひび割れが生じており、震度5強の揺れがあったことが読み取れました。私の自宅は東温市にあるため、大学のある松山市より揺れが小さかったようです。もし理学部の建物内にいたら、かなり驚いて机の下に潜り込んでいたかもしれません。
2011年3月11日、東日本大震災が発生しました。地震そのものは宮城県牡鹿半島の東南東沖130km(深さ24 km)を震源とする東北地方太平洋沖地震で、地震の規模を表すモーメントマグニチュードは9.0で、日本周辺で起こった観測史上最大の地震でした。この地震による巨大津波とこれに伴う福島第一原子力発電所事故による未曾有の災害が発生しました。1000年に1度という規模の大地震と大津波が私自身の生きている同時代に起きたというのはまさに衝撃的でした。太平洋から押し寄せた大きな水の塊が沿岸の町や人々の暮らしを次々に飲み込んでいく様子を写した映像は今でも私の脳裏に深く刻み込まれ、一生忘れることはないと思います。最も深刻な事態は、福島第一原子力発電所事故で、事故の後始末にはあと何十年かかるのでしょうか。原子力を含めたエネルギー問題や地球温暖化問題は、人類の抱えた難題です。21世紀も20年が過ぎようとしていますが、人類はこの問題にどのように立ち向かっていくのでしょうか。大学を定年になる年齢となった私は、これからの若い人たちに期待するしかないのが寂しい気持ちです。
2016年4月に熊本地震が発生しました。この地震の特徴は、震度7を観測する地震が4月14日夜および4月16日未明に発生したほか、最大震度が6強の地震が2回、6弱の地震が3回も発生したことです。大きな揺れを伴う大地震がこれほど立て続けに起こったことはこれまでにないことです。私も訪れたことのある熊本城が甚大な被害を受け、無残な姿がテレビに映し出された際には本当に悲しい気持ちになりました。
2018年9月6日に北海道胆振東部地震が発生しました。この地震の最大深度は7で北海道では初めて記録されたそうです。震源に近い厚真町ではおびただしい数の土砂崩れが発生し、その後グーグルアースを使って観察したその様子には驚かされました。
ここまで、私の記憶に強く残ったいくつかの地震災害を振り返ってきましたが、新しい地震災害が起こるたびに「これまでに私たちが経験したことのない」とか「予想しなかった」という言葉がいつも使われてきたように思います。これは地球と人間の活動のタイムスケールが何桁も異なるためであり、まさに自然なことだと思います。自然災害、特に地震災害はいつどこで発生するのか予測することができません。しかし、災害の発生に備えて常々準備しておけば、被害を最小限に抑えることができると思います。物質的な備えだけでなく、それ以上に心の備えが重要だと思います。これからも悲惨な自然災害は繰り返し発生するのかもしれませんが、その被害が少しでも軽く済めばと願っています。
コロナ渦中で退職を迎えて
入舩 徹男
平成元年4月に愛媛大学に赴任し31年。この3月末にはとりあえず無事に退職を迎えるはずでした。ところが我が国においても猛威を振るいだした新型コロナウイルス(以下コロナ)のおかげで、卒業式をはじめ様々なイベントがキャンセルとなり、気持ちの切り替えができぬままその日を迎えてしまいました。せめてもの慰めは、退職に際して関係者が「業績集」とは名ばかりの、立派な文集をつくってくれたことです。主に卒業生や学会関係者などを中心とした内輪の文集ですが、このような状況の中で何よりの記念となりました。本来はここに書くべき内容も、ほとんどこの文集に尽くされております。祝賀会等での配布機会を失い多数の残部がありますので、ご興味のある方はご請求ください。
退職以降も引き続きセンター長を拝命しましたが、入学式も取りやめになり、授業開始は大幅に延期されました。この間多少時間の余裕もできたので、コロナについて毎日インターネット情報をチェックするとともに、情報源となっている原著論文のいくつかにも目を通しました。この結果、これが知れば知るほど厄介な問題であり、多くの皆さんと同様、先行きの不透明さに大きな不安を感じているのが正直なところです。
コロナ問題は医学・医療の問題にはとどまりません。薬学・化学・生物学はもとより、物理学・数学・工学・経済学・心理学・教育学など、ほとんどありとあらゆる学問分野が関係する、極めて総合的な知識と知恵が必要な問題だと思います。残念ながら私の専門の地球科学はあまり出番がなさそうですが、それでもこの問題に対する科学的な考察は、行動の指針を考える上で重要ではないかと感じています。
例えば人が発する飛沫の飛び方や拡散の仕方は、基礎的な古典力学・統計力学でほぼ理解できますし、感染者の増加の傾向は、数学の基本的な関数や統計処理の知識があれば、日々発表される数値に一喜一憂しなくてもおよその予想がつきます。身近なところでは、マスクの問題があります。通常のマスク繊維の隙間は小さくても5ミクロン程度ですから、0.1ミクロンオーダーのウイルスにとってはザルのようなもの。コロナにおけるマスクの役割は、ウイルスを止めるのではなくウイルスを含む液滴を止めるのが主な役割のはずですが、この点を理解している人が意外と少ないのに驚きます。
我が家でもマスク不足が深刻化し、家内らが毎日マスク作りに励んでくれています。でも数十ミクロンの花粉に対するの同様に、マスクがウイルスもブロックしてくれると思っていたようです。ウイルスとマスクの穴のサイズ感や、ウイルスと飛沫の挙動を理解していないと、せっかくマスクを作っても有効に活用できない可能性があります。また、一定程度の大きさの飛沫をブロックできても、飛沫の水分が蒸発すればウイルスはマスク表面に付着したままでしょう。こうした「乾いたウイルス」は、呼吸により容易に口の中に吸い込まれると考えられますから、(飛沫中のウイルス濃度にもよりますが)こまめに捨てるか洗浄する必要があります。マスコミやインターネットによる情報も、こういった基本的な原理や使い方を、科学的・定量的に示すことは少ないと感じます。
コロナ禍の最中にあって我々退職教員ができることの一つは、それぞれの専門を生かして、この問題を科学的・多面的に考察して、それを一般に向けて発信することではないかと思います。現時点(4月初旬)では、日本においてはコロナによる致死率が比較的低いとされています。それを裏付ける根拠として、マスク文化があるとか、BCGが効いているなど、様々な情報が飛び交っています。もちろんこれらの中には正しいものが含まれる可能性もありますが、その多くは科学的に証明されていない、現象論に基づく希望的解釈にすぎません。我々にできることは、そのような説の根拠や出所をきちんと検証・分析し、その結果をもとに、人々の行動の指針となり得る情報を提供することではないかと思います。
私自身、この半年くらいの間にインフルエンザにかかるとともに、帯状疱疹も経験しました。1か月くらい前までは、「これでコロナにかかればウイルス三冠王」などと冗談を言っていましたが、これらはいずれも免疫力が落ちている証拠。最近の状況を見ていると、明日は我が身と、本気で身辺整理もはじめています。定年後もしばらくは、楽しみながら研究・教育も続けたいと思っていましたが、それも全く見通しがたたなくなりつつあります。
少々暗いご挨拶になってしまいましたが、このような状況の中、今後は自分の専門分野だけでなく、上記のような観点から何らかの社会貢献もできればとの思いを強めています。それなりの覚悟はしつつも、大学人として科学・技術の進歩を信じつつ、この問題の解決に多少なりともお役に立てればと思います。一方で、本稿が印刷になる頃にはコロナ問題が終息に向かい、この挨拶文が笑い話しに終わることを心より期待しています。


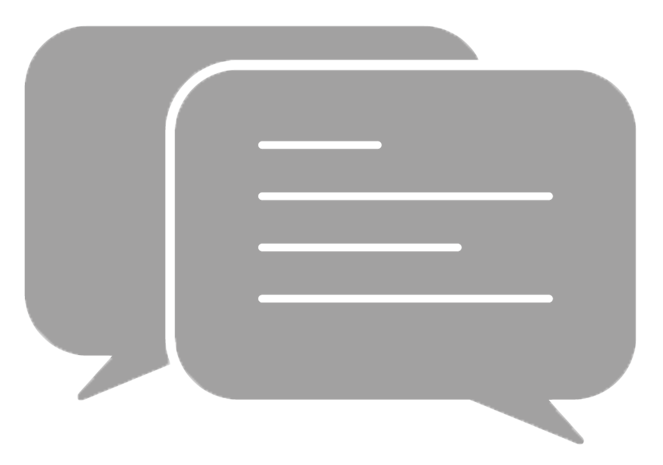 数学・数理情報コース
数学・数理情報コース