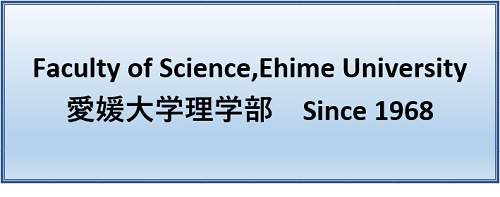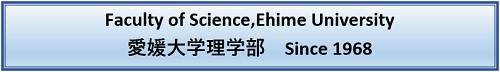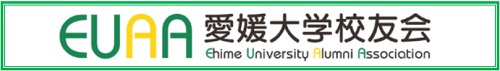教室だより
2022年12月更新
数学教室
皆様におかれましては、ますますご活躍のこととお喜び申し上げます。学生支援をはじめ、日頃よりご支援を賜り誠にありがとうございます。前号(2021年2月発行)以降、この2年間における数学教室の近況をご報告いたします。 教員人事では、令和3年3月に平出耕一先生が定年退職され、令和4年3月に加藤本子先生が琉球大学へ転出されました。また、令和4年2月に岡山大学から寺本有花先生が助教として着任されました。令和4年3月に高知大学から愛媛大学データサイエンスセンター教授として着任された本田理恵先生と、令和4年4月に准教授へ昇任されたデータサイエンスセンターの石川勲先生が数学教室に加わり、現在16名の教員が数学・数理情報コースの教育・研究指導を担当しています。なお、令和5年3月には土屋卓也先生とデータサイエンスセンターの中川祐治先生が定年退職される予定です。数学教室の詳細については、以下の公式サイトでご覧いただけます。 http://www.math.sci.ehime-u.ac.jp/index.html 学生の就職状況に関しましては、令和3年度数学科卒業生のうち14名が大学院に進学し、10名が教員・公務員として、28名が民間企業に就職しました。民間企業に就職した卒業生の半数は情報通信に関わる職に就きました。令和4年度卒業予定者の進路状況についても、おおむね順調とのことです。 新型コロナウイルスの感染拡大を受け令和3年度前期までは遠隔授業が中心となっていましたが、令和3年度後期には可能な限り、令和4年度には原則として対面授業を実施することとなりました。感染防止対策を徹底してではありますが、学生の(マスク越しの)顔を見ながら授業を行えるようになりました。休み時間の談笑や、セミナー室からの議論の声が聞こえると、大学の日常が戻ってきたことを実感します。 令和5年4月に大学院理工学研究科が改組されます。従来の数理科学コースは数理情報プログラムに再編され、数理科学コース担当教員と工学系情報工学コース担当教員が当プログラムの教育を担当します。当プログラムでは、数学の諸分野の高度な理論から応用数学・数理情報・コンピュータ科学に至るまで、学生の興味に応じて幅広くバランスよく学べるカリキュラムが設計されています。平成31年4月に入学した理学部理学科数学・数理情報コースの1期生が当プログラムに入学する予定です。学部・大学院を通じた教育によって、数学・数理情報の能力を身につけ、社会の期待に応えられる学生を送り出していきたいと考えています。今後ともご支援を賜れましたら幸いに存じます。 末筆ながら皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。
(山内 記)
物理学教室
同窓会の皆様には各分野でご活躍のことと存じます。物理学コースの近況についてご報告いたします。理学部で新カリキュラムが導入されて、早4年経過し、新カリキュラムでの卒業研究生が在籍するようになりました。学生により良い教育を提供するための新カリキュラムです。来春旅立つ一期生にはこれまでにも増して活躍してくれることを期待しています。さて、現時点での物理学分野の構成員ですが、理論物理学分野として宗博人(素粒子論)、渕崎員弘(非平衡統計基礎論)、中村正明(物性理論・統計基礎論)、飯塚剛(非線形物理学)、宮田竜彦(統計力学・溶液論)、実験物理学分野として前原常弘(プラズマ理工学)、小西健介(磁性・低温物理学)、近藤久雄(光物性物理学)、天文学分野として粟木久光・寺島雄一・志達めぐみ(X線天文学)、長尾透・鍛冶澤賢・松岡良樹(光赤外線天文学)、清水徹(太陽系プラズマ物理学)、近藤光志(超高層物理学)が在籍し、教育研究活動を行っております。活動内容は理学部で正式採用しております、researchmap (https://researchmap.jp/researchers)からたどっていただければお分かりになられるかと思います。幅広い分野で多くの研究成果を公表できております。ただ、残念なことに、2022年度末をもって宗博人が定年退職の予定です。教育・研究、ならびにコースの管理・運営で尽力していたので、コースとしては大きな損失とになります。 2022年も新型コロナが猛威をふるい、11月中頃には第7波のピークがあり、国内で過去最多の感染者数を記録しました。新型コロナの感染者が出始めた2年前は、在宅勤務など活動に大きな制約がありましたが、今は感染防止対策等のコロナの知識が蓄積され、教育研究活動もコロナ前に戻りつつあります。この間、学生への教育面で遠隔の便利さを実感できましたが、改めて対面のありがたさもわかった気がします。また、2月からのロシアによるウクライナ侵攻や円安の影響で、国内での物価が上昇しています。エネルギー価格の上昇は、電気代高騰という形で大学での教育研究活動も圧迫しています。一刻も早くに戦争が終結し、再び安定した環境が訪れるよう切に願っています。 こうした状況下、卒業生の皆様におかれましても,一層のご支援・ご協力を賜れば幸いです。末筆ながら,皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。
(粟木 記)
化学教室
2019年度の理学部改組により,化学科は理学科化学コースとなりました。2022年度より新カリキュラムの学生が研究室に配属されて研究を開始したところです。2020年から新型コロナウイルスの影響を受けて、苦しい状況が続いてきました。研究や教育への制限は大学本来の姿が変わってしまった時期でした。2021年2月は修士論文審査会を感染対策をしておこないました。卒業論文発表会は人数を制限した対面と遠隔のハイブリッド化で田上瑠美助教と愛化会のご尽力で行いました。2022年度になって、やっとコロナ対策をしながら、実験以外の科目でも対面での授業が開始されたところです。遠隔授業の続いたこの2年間、今の4回生、3回生への影響は計り知れずあります。4回生にとって研究生活で挽回できることを願っているところです。 2022年度になってやっと海外の学会での発表も許可されるようになってきました。多くの先生方が海外出張されています。国内での学会も対面で開催されるようになり、研究活動の上では対面での議論の大切さを感じているところです。学生、教員の両方にとってまだ困難な状況が続く中,このように皆の努力と協力,周囲のご理解のもとで,教育研究に取り組んでいます。 構成員としては2021年3月をもって,長岡伸一教授が定年退職を迎えられました。2022年4月から田上助教(特定教員)が助教に昇進されました。2023年3月をもって佐藤久子教授が定年退職を迎えます。宇野英満教授は引き続き理事として大学の運営を当たられます。2022年度現在の研究室と教員の構成は次の通りです。①固体物性化学・反応化学系:〔固体物理化学〕内藤俊雄・山本貴,〔構造化学〕小原敬士・垣内拓大,〔無機化学〕高橋亮治・佐藤文哉,〔複合体化学〕佐藤久子,②分析化学・生物化学系:〔分析化学〕座古保・島崎洋次,〔生物化学(プロテオサイエンスセンター)〕杉浦美羽・小川敦司,〔環境化学(沿岸環境科学研究センター)〕国末達也・野見山桂・田上瑠美,③有機合成・物質科学系:〔有機化学〕宇野英満(理事)・奥島鉄雄・高瀬雅祥,〔有機化学(学術支援センター)〕谷弘幸・倉本誠・森重樹。以上,20名の教員で,理学部化学コース・大学院理工学研究科分子科学コースの教育研究を行っています。 厳しい社会状況ではございますが,引き続き卒業生・同窓会の皆様からのご助言・ご支援をお願いいたします。
(佐藤 久子 記)
生物学教室
皆様におかれましては,ご健勝のことと存じます。生物学コースの近況についてご報告致します。新型コロナウイルスは,様々な行事に今もなお大きな影響を及ぼしておりますが,修士論文審査会,卒業論文発表会は予定通りに実施することができました。人事に関しましては,公募により選ばれた加藤大貴助教が令和3年3月より新たに赴任されました。加藤先生は植物学を専門としており,コケ植物の進化を研究されております。一方で,井上雅裕教授が令和3年3月に定年退職を迎えられました。長らく生物学教室での教育と研究に貢献されてきた井上先生に心より感謝致します。 改組により生物学科は生物学コースに変わっておりますが,生物学教室ではこれまでどおり,「形態形成」,「生理・適応」,そして「生態・環境」の三つの分野を柱として教育と研究を推進しております。形態形成領域では佐藤康(植物形態学),金田剛史(植物形態学),高田裕美(発生生物学),村上安則(進化形態学),および福井眞生子(進化形態学)の5名,生理・適応領域では佐久間洋(植物生理学),加藤大貴(植物生理学),北村真一(魚類感染症学)および仲山慶(環境生態応答学)の4名,生態・環境領域では中島敏幸(生態学),井上幹生(生態学),畑啓生(生態学),今田弓女(生態学)および岩田久人(環境毒性学)の5名が,それぞれの研究室を運営しております。令和4年度においては卒業研究生45名,博士前期課程の大学院生27名,博士後期課程の大学院生3名が各研究室に所属して研究に励んでおり,優れた研究成果を挙げております。 先述の通り,現在も新型コロナウイルスの影響が色濃く残る状況が続いております。しかし,令和4年度には授業の多くが対面形式となり,かつての授業風景が再び見られるようになってきました。コロナ禍で様々な活動に制限がかけられ,沈みがちだった学生の表情にも明るさが戻ってきたように思います。新型コロナウイルスへの対応の過程で,教員の創意工夫により,多くの授業でオンライン教材が整備されたことは,厳しい状況が生物学コースの教育環境を進化させたと言えるかもしれません。今後も在学生の皆さんができる限り充実した学生生活を送ることができるように最善を尽くす所存です。卒業生の皆様からのご助言やご協力を頂けると大変ありがたく存じます。最後になりますが,卒業生の皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。
(村上 記)
地学教室
理学部同窓会の皆様におかれましては,各分野でそれぞれにご活躍のことと存じます。地学(地球科学)教室の理学部同窓会前号(12号:令和3年2月発行)以降の近況を報告いたします。 人事では,令和3年2月に,固体地球科学がご専門の井上紗綾子先生が地球深部ダイナミクスセンター(GRC)の助教として着任されました。令和3年3月には,比較惑星学がご専門の桑原秀治先生がGRCの助教として着任されました。また同月に,GRCの西真之先生が大阪大学へ転出されました。令和3年3月末日をもって,Alexandra Abrajevitch講師が退職されてロシアへ帰国され,GRCの大藤弘明教授(東北大学)のクロスアポイントメントが終了しました。令和3年4月に,鉱物学がご専門の延寿里美先生が助教として着任されました。また同月より,掘利栄教授が副学長(ダイバーシティ担当)に任命されました。 現在,地学教室では,学部専任教員7名(地質学鉱物学分野),GRC所属の教員11名(固体地球物理学分野),沿岸環境科学研究センター(CMES)所属の教員4名(海洋学分野)で,研究と教育とをおこなっています。平成28年度に社会共創学部に転出された榊原正幸教授は,大学院では引き続き地学教室での教育をおこなっておられます。学部専任教員が7名で他のコースの半数程度であり,管理運営や野外実習の指導における教員の負担が他コース以上に大変な状況は相変わらずです。 教育面では,コロナ禍がある程度収束して,日常を取り戻しつつあります。その中で,コロナ禍で発展した遠隔での会議や授業などの良い点をある程度引き継ぎつつ,原則として対面授業がおこなわれています。令和5年3月に,理学部改組(令和元年度)後に入学した学生が初めて卒業を迎え,社会へと送り出される予定です。また,令和5年4月には,大学院の改組が予定されています。現在,大学院理工学研究科は5専攻で,大きく理学系と工学系とに分かれていますが,改組後は1専攻(理工学専攻)になります。博士前期課程は,専攻の中に4つの基盤プログラムがあり,その中に既存のコース(分野)が入る形になります。地球進化学分野は,物理・化学・生物とともに,自然科学基盤プログラムの中に入ります。名称も,「地球進化学」から「地球科学」に変更されます。博士後期課程は,基盤プログラムはなくて,理工学専攻の下に地球科学分野が設置されます。 学部・大学院ともに大括りでの教育体制となりましたので,これまで以上に多様な学生の教育をしていくことになると予想されます。地学教室の同窓生の皆様には,今後ともご支援とご協力を頂けたら幸いに存じます。最後に,同窓生の皆様の益々のご活躍とご健康を心より祈念いたします。
(鍔本 記)


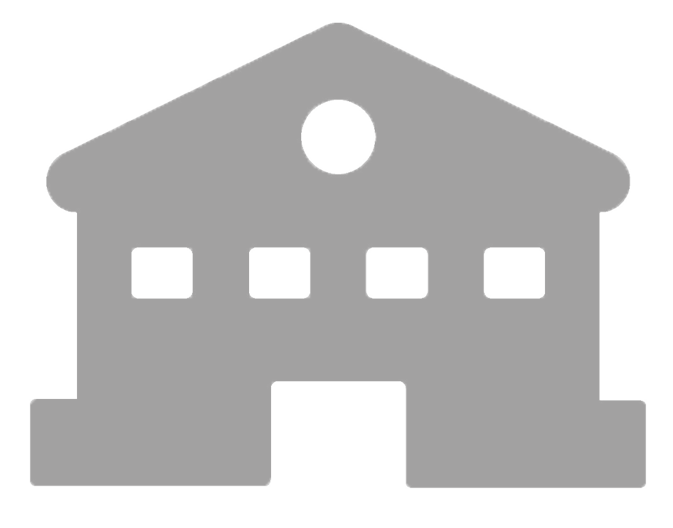 数学教室
数学教室