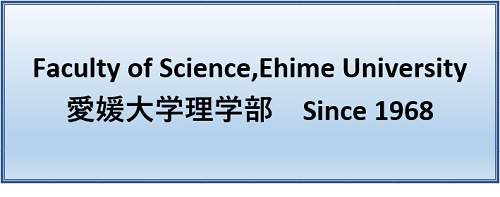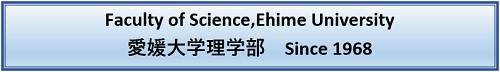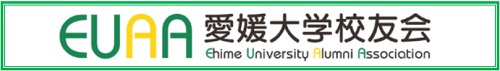母校の窓>2018
2018年度・2017年度末退職の先生方からのメッセージ
退職にあたって
栗栖 牧生
 松山が人生で一番長く過ごした町になってしまったと思う人は退職する教員には多いのではないでしょうか。松山は本州へのアクセスの大変さを我慢できれば本当に住みよい処と思います。穏やかな秋、冬の気候も人々の暖かい気持ちも本当にありがたいです。郊外に出ればすぐに1,000mを超える山々、手つかずの自然が待っていてくれます。毎朝、私は自宅のベランダ越しに遠く見るひどく突っ張って鎮座する山々と隣家との境に少しだけみえる伊予灘にあいさつをしてから出勤していました。
松山が人生で一番長く過ごした町になってしまったと思う人は退職する教員には多いのではないでしょうか。松山は本州へのアクセスの大変さを我慢できれば本当に住みよい処と思います。穏やかな秋、冬の気候も人々の暖かい気持ちも本当にありがたいです。郊外に出ればすぐに1,000mを超える山々、手つかずの自然が待っていてくれます。毎朝、私は自宅のベランダ越しに遠く見るひどく突っ張って鎮座する山々と隣家との境に少しだけみえる伊予灘にあいさつをしてから出勤していました。
前任地を離れるときに理学系出身教員から異口同音に言われたのが、“理学部によく就職口がありましたね”、ということです。理学部では高等教育の商業化もそれほど進んではいないだろうし、じっくりと教育・研究に打ち込める環境があるからがんばれよというエールと解釈しました。前任地では新研究科の立ち上げ業務に従事するというということで採用されていたのですが、それも軌道になってから同年代の同僚が次から次と新天地に転出していたにもかかわらず、出遅れてしまった挙句、なんとかたどり着いた松山での職です。大学教員公募に52連敗された方のWEBサイトが有名ですが、応募し続けることは大事です。
愛媛大学は私にとって4つ目の職場になります。前任地に赴任するときもそうでしたが、何か良い出会いはないだろうかという希望を持ち、伊予の国にやってきました。はたしてその良い出会いはあったのか、その存在すら気がつかずに無為に時間だけ浪費してしまったのか日々反省するだけですが、松山に来てから驚いたことと定年を迎えて思うことを書いてみます。
はたして愛大理学部はどうだったのか。分かってはいたものの、基礎的な研究環境が整備されていなかったことはすぐに困ったことの一つです。同業者は少ない、研究資産は整備されていないなど、中小規模大学の特徴がよく現れていると思いました。しかし、幸いなことに概算要求などにより固体試料の構造評価と種々の物性評価ができる最先端の評価装置群が設置できたことには本当に驚きました。それまで大型予算請求では何連敗かしていましたので、それなりに準備をしっかりと進めたのが良かったのか、とにかく当たったのは奇跡であり大きな喜びとなりました。一方、通常校費の方は、赴任当初は教育・研究予算がそこそこに支給されていたように思います。しかし、年々、その予算も削減され内部と外部からの競争資金が獲得できなければ、じっと我慢して過ごすような雰囲気になってきたように思います。いわゆる基礎研究にも潤沢な研究資金とこれも研究機関がサポートすべき環境の整備は必要です。
次から次へとやってくる新手の業務への皆様の抵抗力のすごさには驚きました。たくましくも思えました。失うものはあっても得るものがないのであれば、これも仕方がないものと傍観者的にみていました。学内の教員への評価制度も年々姿を変えながら?実施されていますが、評価項目が過度に詳細になりすぎていること、非常に短期的かつ見栄えのよい業績が過大評価されすぎているように思います。こんなことばかりが続けば、研究者それぞれが属するであろう階層は固定化され、研究者も同質化されてしまうのではないでしょうか。そうなれば、無駄な労力の消費はすぐに教育研究の質の劣化につながることは容易に想像できます。
長く学部生と接することのない環境にいたためか、学部のカリキュラムの中身など考えたこともなかったのですが、大綱化以降の流れの中でそうなったのか、提供できる授業科目は少なくなっており、その分各種のスキル習得に直結したいい意味では実践的知識の習得を目指すことに授業が多くあったことにも驚きました。カリキュラム自体、窮屈に感じました。教養教育という言葉は姿を消したように思えました。大学教育によって養成される知識と技能は実社会では役にたたない、これは古くから言われてきたことであり、日本の大学の特質なのでしょうか。
なんだかんだと言っても大学が元に戻ることはありませんし、そうなれば衰退の一途をたどることになると思います。大学が今後どうあるべきかについてまで言及できませんが、愛大理学部には教職員の間に良好な信頼関係が構築されてきたように思います。構成員間の意思の疎通も図りやすい組織ではないでしょうか。おかげ様で気分良くすごさせていただきました。構成員の積極的参加による合意形成はこれからの荒波に対処していくには効果的かと思います。
定年まで好きな研究ができたことは本当に幸せなことと、これまで親身にお世話になりました諸先生方をはじめ事務職員の方々、学生諸氏に感謝します。志半ばで鬼籍に入られた方々も多くありますが、あのときそのときを思い出して自問自答することが多くなりました。私自身は私の運命の主人公ですが、すべてのことを自身だけで決めているわけではないと思っています。良きにつけ悪しきにつけ周りによって造られていること、また、造られていくことを実感するときがあります。この意味でこれからも人との出会いを大事にしていきたいと思います。
最後になりますが、今後の愛媛大学、理学部のますますの発展と愛媛大学理学同窓会の皆様の益々のご活躍とご多幸を祈念して私の感謝の言葉とさせていただきます。
定年退職を迎えて
加納 正道
33年と6ヶ月に及ぶ愛媛大学での生活でしたが、過ぎてしまえば「あっという間」でした。この間、いろいろなことに頑張ってきたつもりですが、では何ができたかいうと、たいしたことができていなかったことに気づかされます。しかしながら折角このような機会をいただきましたので、反省の意味も込めて33年と半年を断片的に振り返らせていただきます。
私が愛媛大学に赴任したのは昭和60年(1985年)10月で、振り出しは教養部生物学教室の講師でした。これはちょうどその頃、法文学部に夜間主コースができ、その教養教育のための定員がついたことによるものです。そこから教養部での生活が始まるわけですが、教養部での最大のミッションは教育であり、多くの講義や学生実習が待ち構えていました。私には本来の教養部での講義に加え、法文学部夜間主での講義があり、理学部での講義もありました。その当時、教養部の生物学教室と理学部の生物学科はうまく連携しており、人事においても理学部にはない分野の教員を教養部で揃えるようにしていました。理学部にはなかった動物生理学が専門の私が採用されたのも、そのあたりの事情もはたらいていたようです。従って、理学部における動物生理学の講義を担当するのは、半ば当たり前のような雰囲気でした。また、理学部の卒論の学生も引き受けて研究指導を行っていました。そのような教育中心の大学生活の中で、いかにして研究にための時間を作り出すかがその当時の課題でした。研究中心の理学部がとても羨ましく感じた時期でもありました。
平成3年(1991年)、海外で研究する機会が訪れます。本来の私の専門は昆虫(コオロギ)を使った神経行動学なのですが、米国ミズーリ州セントルイスにあるワシントン大学の菅乃武男先生が、コウモリの研究をしに来ないかと誘ってくださったのです。菅先生はコウモリのエコロケーションにおける大脳聴覚野の研究の第一人者でありますが、実は奇妙な(?)縁がありました。菅先生との最初のつながりは、北大時代の私の恩師である下澤楯夫先生が、かつて菅先生のもとで研究をしていたことによるものですが、私が赴任した教養部の生物学教室におられた池田洋司先生(故人)も米国におられた時に菅先生と同じ研究所だったのです。両先生の推薦ということで、菅先生もたいそう喜んで私を迎えてくれました。米国への出張は2年間という長丁場で、しかも妻と子供三人を引き連れてでしたので色々と大変でしたが、多くの貴重な経験もできました。
平成5年(1993年)に帰国しましたが、この年の松山は平成の大渇水の年でした。おかげで、水のタンクを持ち上げようとした妻は、帰国早々ギックリ腰になってしまいました。実は、私が帰国する直前のセントルイス(というよりも、ミシシッピ川流域の多くの場所)は中西部上流域での大雨により洪水になっていました。これは米国史上最大の被害をもたらした洪水とも言われています。私も研究室の同僚達と支援物質の仕分けのボランティアに行きました。米国で洪水にあい、帰国したら大渇水というわけで、水にたたられた忘れられない年でした。
それから間も無く、大きな出来事がありました。それは平成8年の教養部解体です。その直前までは教養部の新しい校舎を作る計画が進められ、すでに図面まで出来上がっていました。その矢先の組織解体ということで、一生懸命に教育を行ってきた我々は非常に複雑な心境でした。紆余曲折があり、私は理学部に所属することになりましたが、不本意な異動を強いられた教員もいたようです。ただし理学部に移籍したと言っても、理学部本館の改修工事や昆虫の飼育設備等の都合で、しばらくは旧教養部の建物(共通教育棟)に居続けました。理学部への引っ越しができたのは、それから11年も経った平成19年のことでした。
所属が理学部へ移った後、時間的に少しは余裕ができるようになりました。すなわち、教養教育を行う部局がなくなったので、それまで教養部の教員が担当していた教養教育を全学の教員で分担することになったからです。もちろん私も自分の担当分の講義は受け持ちましたが、それまでに比べると随分と楽になりました。そのおかげで、研究も少しずつ良い方へと向かって行きました。科学研究費補助金はそれまでもほぼ絶え間無く獲得できていましたが、平成11年度から13年度にかけては大型の科学研究費である、「特定領域研究(A)・微小脳システムの適応的設計」に計画班代表として参画することができました。この時の予算で、いろいろな実験機器を揃えることができたことが、後の研究の進展に繋がりました。この特定領域研究では、多くの関係者が参加しての研究会やシンポジウムを松山で開催しましたが、研究室のスタッフは私一人ですので、会場や宿泊の手配、あるいは懇親会の準備等でとても大変でした。やはり、何もしないでうまい汁だけを吸うことはできないことを痛感しました。
愛媛大学における最後の数年間は、執行部の一員として理学部の管理運営に力を注ぐ(注がされる)ことになりました。特に最後の1年間は、評議員・副理学部長としてのみならず、理学部設置50周年記念事業等を取り仕切る2つの委員会の委員長を任せられました(このことは、別に書かせていただいております)。管理運営のような仕事はあまり得意ではなく、むしろ嫌いな分野なのですが、どういうわけか不得意な仕事で大学生活を締めくくることになってしまいました。あまり理学部のお役には立てなかったことと思いますが、ご容赦願いたいと思います。 理学部は来年度より改組により一学科となります。是非この変革をチャンスとして、大きく発展していただきたいと思います。これからは外から理学部の発展を見守って行きたいと思います。
愛媛大学での31年間
和多田正義
東京で生まれ育ち、東京の大学を卒業し、ショウジョウバエの研究をしていた私が、愛媛大学に職を得て31年になりました。愛媛大学に勤めるまでには、大学院を終了した後に、当時は渋谷区南平台にあった(現在は千葉県我孫子市)山階鳥類研究所で2年半、静岡県三島市の国立遺伝学研究所で半年、アメリカのノースカロライナ州にあるNIHの研究所(NIEHS)で2年ほど研究生活を続けていました。NIEHSの上司は、テニュアを取るために自身の研究を中断して、申請書を審査する仕事にかかりきりになってしまったことから、研究室は私と黒人のテクニシャンと2人で運営することになり、そのために行ったときから多くのトラブルを抱えました。このままでは大した業績もあげられず、日本に帰れないのではなかと思っていた頃に、愛媛大学の教養部に講師に応募しないかという話があり、縁があって愛媛大学に採用されました。爾来、愛媛大学で教育研究に励み、無事に退職するまで勤めさせていただきました。
愛媛大学に勤めた31年間のうち、始めの8年間は教養部で教育研究を行っていました。アメリカで愛媛大学の前任の先生の時間割を見たときには、普通の量のノルマだったのですが、前任の先生はその時全学の学生部長をされていたので、講義時間が半分になっていて、教養部では2倍の講義数になっていることが後で分かりました。しかし、その分教養部では研究費は多いことが分かり、とりあえずの研究費には困りませんでした。しかし、実験スペースは実に狭く、私が個人的に専用できる実験スペースは2坪の恒温室だけでした。また、全国的にも珍しいと思われる理学部生物学科の卒業研究生の指導をするシステムができており、私も初年度から2名の卒業研究生を指導するなど、理学部の先生と同様に卒業研究生や大学院生の指導を行なっていました。31年間に指導した学生は80人ほどでそれほど多いわけではありませんが、着任2年目に指導した津村英志さんについてはここに記しておきたいと思います。津村さんは私の所で大学院博士前期課程を修了し、愛媛県松野町にあるおさかな館に勤め、館長をしていました。
彼が館長をしている時には、学生たちを連れておさかな館に行ったり、テレビ等でその活躍ぶりを拝見していましたが、2018年2月に50歳の若さで早世されたのは、返す返すも残念でなりません。
1996年に全国の国立大学の教養部が廃止され、私は理学部の所属となりました。その当時の理学部本館は改修の予定で、今ではミュージアムになっている教養部の建物でしばらくの間、教育研究を続けていました。理学部へ所属してすぐに私は10ヶ月の在外研究をする機会を与えられました。行き先はアメリカのアリゾナ大学のマーガレット・キッドウェル教授の研究室でした。キッドウェル教授はショウジョウバエのハイブリッド・ディスジェネシスという現象を発見された方で、この発見を契機にショウジョウバエの分子生物学が発展したことで著名な先生でした。キッドウェル教授は、1996年当時はハイブリッド・ディスジェネシスをひき起こす要因であるP因子というトランスポゾンの分子系統の研究を行なっていました。私は日本で採集したさまざまなショウジョウバエを持参し、研究するつもりでしたが、私が行った時にはP因子の研究はあらかた終わっており、私自身は別の遺伝子を使って分子系統の研究を行いました。アメリカの大学や研究所では東部と西部で研究に対するふんいきが異なるということは聞いていました。NIEHSに行った時はアメリカ東部の研究所でポスドクだったということもあり、研究漬けの生活をしていました。一方、アリゾナ大学では西部の大学ということで学生に囲まれた生活だったので、アメリカの大学生の様子も良くわかり、私も大学生活を大いに楽しむことができました。
キッドウェル教授の研究室に行くために収集しておいたさまざまな種の系統が縁となり、2002年から文部科学省のナショナルバイオリソースプロジェクトに関わることになりました。このプロジェクトは日本では個人の研究者や外国のストックセンターに頼っていた生物の系統維持を、国レベルで戦略的に収集・維持・提供しようとするもので、ゼロからのスタートになりました。私はこのプロジェクトに分担機関として最初から参加し、定年退職の年まで17年間継続することになりました。ストックセンターを開設するにあたり、私が収集していたショウジョウバエだけでは全く足りないので、始めの数年間は日本中を採集することになりました。また、今までにないプロジェクトのために理学部の事務の担当者の方々にはたいへんお世話になりました。このプロジェクトに関わったために、私の研究時間は大方このプロジェクトに割かれ、土日も大学に来るような生活になってしまいました。このボランテアともいうべきプロジェクトでは当初予想していた悪いことばかりでなく、国内外の多くの研究者と接点を持つことができ、そのうちのいくつかは共同研究となって望外の実を結びました。
同窓会の原稿を頼まれた時は、2000字を書くのは大変かと思っていましたが、いざ書き始めてみると書くことが多く、すぐに2000字を超えてしまいました。最後に31年間に及ぶ教員生活で指導した学生だけでなく、多くの学生、教員、職員の皆様に親しくご交誼いただいたことに深く感謝していることを申し添えておきます。皆様方の益々のご発展とご健康を心からお祈り申し上げます。
愛媛大学での40余年を振り返って
小玉 豊美
 先日、東理学同窓会長から会報の原稿執筆依頼をいただき、軽い気持ちでお引き受けしましたが、なかなか筆が進まずクリスマスイブの日に書いています。発行予定は来年2月とのことですから、私はその頃に還暦を迎え、3月には定年退職となります。思い起こせば、昭和52年に愛媛大学に採用されてから、早や42年が経ちました。
先日、東理学同窓会長から会報の原稿執筆依頼をいただき、軽い気持ちでお引き受けしましたが、なかなか筆が進まずクリスマスイブの日に書いています。発行予定は来年2月とのことですから、私はその頃に還暦を迎え、3月には定年退職となります。思い起こせば、昭和52年に愛媛大学に採用されてから、早や42年が経ちました。
東会長には、最初の配属先の教養部化学教室でお世話になり、当時は学生実験の準備などもお手伝いさせていただきました。社会人1年生の私にとって、全てがとても新鮮で得るものがたくさんあり、教員や学生との関わり方、仕事に対する責任感や姿勢も学びました。
その後、理学部に異動になり、地球科学科事務室で5年間、優秀な先生方、ユーモアのある学生達そして理学部事務職員とともに、愛媛大学で一番楽しかったと言える時間を過ごしました。しっかり者の娘が誕生したのもこの頃です。地球科学教室では、教員の流動性が高く、小松元学長や入舩現GRCセンター長他、多数の先生方をお迎えして、さらなる地球科学科の発展に向けての基盤が作られていました。
さて、平成16年4月、国立大学法人化によって、国立大学は大きく変わりました。管理運営は、学長と理事で構成する役員会が大学経営の方針決定から業務管理まですべてに責任を持つという構造になり、教職員に関する人事管理や労務については、それまでの公務員法制から一般の労働法制へと大きく変化しました。身分は公務員から、団体職員になったわけです。
私はと言うと、法人化を工学部総務係長で迎え、本部総務課、国際連携課、人事課、医学部と異動し、再度、理学部とのご縁があって、平成29年4月から理学部事務課長を務めさせていただいております。前職の医学部総務課での2年間は、熊本地震でのDMAT・DPAT派遣、寄附講座設置、ドクターヘリ運航開始、第一種感染症病床施設運用開始、防災・備蓄倉庫の整備などを担当し、対外的にも多くの方々と関わり多忙でしたが、理学部での業務にも役立つ貴重な経験をさせていただきました。
本学は第3期中期目標中期計画において、平成31年4月に理学部、工学部の組織改編を実施することを目標に掲げております。理学部では、平野学部長の指揮の下に、「改組」を合言葉のように平成29年4月から毎週、改組WGにおいて議論をつくし、現行の5学科体制から、分野横断機能とキャリア形成機能を強化した1学科5教育コース3履修プログラムの教育体制に改組することになりました。平成31年度の理学部改組に関する設置審査が終了し、平成30年7月6日に理学部の設置報告書が文部科学省に受理され、現在は平成31年度入学生の受入準備や改組の広報活動に取り組んでいます。
また、もう一つの大きな仕事は、理学部設置50周年記念事業でした。まずは、理学部改組を行っておりましたので、記念誌刊行委員会や記念事業実施委員会の設置が平成29年11月となりました。その頃、平野学部長と加納委員長が、東会長に理学同窓会との共催という形での、理学部設置50周年記念事業のご相談をして、共催が決まった以降は、加納委員長が先頭に立って、理学同窓会とともに、企画調整をされました。
特に予算面では、理学同窓会にご支援をお願いしたところ、理学部の予算事情をお汲み取りくださり、理学同窓会の過分なお心遣いによって、お陰様で50周年記念事業を盛大に実施することができました。また、50周年記念誌も皆様のご協力により、無事に刊行できましたことを大変嬉しく思います。ご寄稿くださった執筆者の皆様に改めて感謝申し上げます。記念誌は残部がございますのでご希望の方は、理学同窓会事務局までご連絡ください。
11月11日(日)、国際ホテル松山で開催した式典には神野一仁愛媛県副知事、梅岡伸一郎松山市副市長、柳澤康信前愛媛大学長、髙橋祐二愛媛大学校友会会長をはじめ、愛媛大学ステークホルダーの皆様、理学同窓会の皆様、退職教職員等約130人の皆様にご出席いただきました。
記念講演会では、入舩徹男地球深部ダイナミクス研究センター長が「地球深部科学から超高圧材料科学へ」 ~愛媛で生まれた世界最硬ヒメダイヤとその応用~ と題して講演を行い、歴史を振り返りつつ現在まで積み上げてきた世界レベルの研究の進展をユーモアも交えながら語られました。記念祝賀会では、平野学部長の開会挨拶、小松正幸元愛媛大学長の挨拶に続く鏡開きの後、柳澤前学長に乾杯のご発声をいただきました。理学部卒業生等による琴、尺八、ピアノのアンサンブルや理学部の歴史を綴るスライドの上映などの催しも行われ、理学部設置50周年を祝うに相応しい盛大な会となりました。
さて、記念祝賀会でもご報告いたしましたが、市道拡張工事のため、理学部正門横で、長い年月理学部を見守り続けた3本のソメイヨシノ(推定樹齢50年以上)が、この秋に伐採されました。理学部では、昨年3月末に農学部にご相談をして、5月連休頃から農学部大橋広明先生のご協力をいただき、挿し木や取り木で繁殖を試みています。大橋先生によると順調に発根しており、先月には、取り木した枝に数輪の花が咲いていたそうです。近い将来、この桜の子孫が理学部構内のどこかで復活することを楽しみにしています。
また、宇野理事のご発案によって、伐採された原木を農学部演習林で桜チップにしていただき、記念祝賀会では、袋詰めをご自由にお持ち帰りいただきました。燻製作りは、初めての方でもフライパンなどで簡単に挑戦できるようですが、皆様、いかがだったでしょうか。
大橋先生には、桜の挿し木を快くお引き受けいただき、今夏の猛暑の中何度も足を運んでいただきました。また、桜チップ作りでは関係の皆様に大変お世話になりました。この場をお借りして、御礼申し上げます。
このように、私の愛媛大学での最後の2年間は、理学部改組と50周年記念事業の2つに集約できます。設置審査も記念事業も無事に終わり、関係する皆様に大変感謝しています。そして、40余年間、多くの貴重な経験をさせていただいた愛媛大学にも感謝の気持ちでいっぱいです。
さて、退職後の私の進路ですが、周囲から働けるうちは働いた方がいいよ。税金くらいは働かなくちゃ! ずっと働き続けたんだから、しばらく休んだらいいよ。もう仕事しなくて、いいんじゃない。エトセトラ。これまでの私は、定年退職を心待ちにして、再雇用は全く考えてもなかったですが、ここにきて、周囲も私も、ざわざわしている今日この頃です。
最後に、ご指導いただいた諸先輩やこれまでお世話になった皆様に改めて御礼を申し上げるとともに、皆様の益々のご健勝とご活躍、理学同窓会の更なるご発展を心よりお祈り申し上げます。
愛媛大学理学部での思い出
林 秀則
昨年3月に無事定年を迎えることができました。在職中にご助言、ご指導くださった諸先生、無理難題に対しても快くご尽力をしてくださった職員の方々、また研究室で生活を共にした卒業生の皆様はじめ、多くの方々に心より感謝申し上げます。
私は平成7年2月に理学部化学科に赴任し、平成15年からは無細胞生命科学工学研究センター(平成25年からプロテオサイエンスセンターに改組)における研究を本務としつつ、約23年間、理学部化学科の学生の教育を担当してきました。平成の時代の約8割、50周年を迎えた理学部のほぼ半分の期間を過ごしたことになります。この間、大学は大きな変革を求められ、様々な改革が試みられ、いろいろな意味で大きく変貌を遂げたと感じます。敢えて言うなら「教官ファーストから学生ファーストへ」の意識の変化です。組織的には平成16年の国立大学法人の設置であり、これに伴い「教官」は「教員」に変わり、一方で少子化に伴う入学志願者の減少とゆとり教育の相乗効果によって大学生の気質が変わり、これらの変化への対応として業務形態や組織体制の変革を余儀なくされる一方、入学志願者の確保に奔走しなければなりませんでした。このような変動の時代を経ても、著名大学に引けをとらない実績を残してきた本学の活動の一端を担えたことは、ある意味充実した教育研究生活が送れたものと思っています。
着任前には、学生時代のタンパク質を材料とした生物化学の研究から物理化学講座でラマン散乱や赤外吸収などの振動分光学を利用した研究へ、さらには基礎生物学研究所における植物の遺伝子操作という、一見、脈絡のない研究生活を送ってきました。おそらくそれが幸いして、理学部化学科に新設された研究室において、化学科でありながら生命を扱うという当時の地方大学としては珍しかった使命をいただきました。採用人事に携わられた河野博之先生、小野昇先生の「生命は面白い、これからは生命科学の時代だ」という先見の明のとおり、いまやiPS細胞、癌治療、ゲノム編集などという言葉を日常的に聞くようになりました。赴任の際、河野先生が「生物を扱うのに水は必須でしょ」とおっしゃって、化学系の実験室には珍しい大きな流しが付いた中央実験台のある研究室を用意して下さったのには感激しました。
私が赴任した平成7年は、ある微生物の全ゲノム配列が解読されたという歴史に残る年でした。しかし、遺伝子を扱った実験はまだまだ普及しておらず、例えばキャピラリ型のDNAオートシーケンサー(自動塩基配列解読装置)を導入したのは私の研究室が愛媛県では最初でした。その後、愛媛大学にも遺伝子実験施設が設置され、同型の装置も導入され、農学部や医学部の多くの先生方が利用されました。研究室がスタートしたときには、化学を学ぶために進学した学生が生物を対象とした研究に興味を持つだろうかという不安はありました。しかし「生命現象は化学反応の積み重ねである」と強調したこと、そして遺伝子操作などの実験は、正しい濃度の溶液を正しい比率で混ぜ合わせるという、極めて化学的な実験であったため、研究室に来た学生はためらうことなく取り組んでくれました。その結果、私自身は実験に取り組む時間が少なかったですが、学生が重金属結合タンパク質や熱ショックタンパク質に関して、また塩ストレス耐性や高温ストレス耐性の遺伝子操作に関して、いつも興味ある実験結果を報告してくれ、何度となく感激したことを思い出します。
無細胞生命科学工学研究センターでの使命の一つは、遠藤弥重太先生が開発されたタンパク質合成技術の普及の一環として、高校でも使える教材キットを開発することでした。私が赴任した頃、社会的には理科嫌い、理工離れといった風潮が懸念される一方、大学としても理工系学部への志願者確保が必定と考えられたため、社会貢献の一環として学外者対象の実験教室や高大連携授業などに取り組みました。平成14年には文部科学省によるスーパーサイエンスハイスクール事業が始まり、理学部からの運営指導委員の一人として高校の先生方と理科教育について議論を重ねました。大学でも平成17年からスーパーサイエンス特別コースが開設されることになり、多くの先生方と科学者・研究者に必要な素質やその育成プログラムを検討しました。その後もこれらの活動を継続する過程で、前述のタンパク質合成技術を取り入れた学習プログラムを考案し、市民対象の公開講座、高大連携授業、教員対象の研修授業などにおいて、多くの方にコムギ胚芽抽出液を用いたタンパク質合成実験を体験してもらいました。通常の講義室や会議室であっても、容器の中に液体を加え、1~2時間経つと、クラゲの遺伝子から作られたタンパク質が蛍光によって簡単に観察でき、その輝きに会場から感激の声が聞かれることも多々ありました。この実験教材はプロテオサイエンスセンター客員教授の片山豪先生によって改良され、その内容が高校の教科書「生物」の探究活動として掲載される一方で、必要な教材キットが学内発のベンチャー企業から市販もされるようになりました。
現在、理工学研究科特命教授を拝命し、高校生を対象としたJSTの科学技術人材育成プログラム(グローバルサイエンスキャンパス)の実施をお手伝いさせていただいています。今後も多くの方のご協力をいただき、若い世代に科学の感動を与えることができるよう努力したいと思っていますので、なにとぞよろしくお願い申し上げます。
末筆になりましたが、理学部の発展ならびに皆様のご活躍とご健勝を祈念しております。
松山で過ごした日々
山本 明彦
赴任以来、13年間を理学部で過ごし、定年を迎えることとなった。退職に伴い挨拶を寄稿する機会をいただいたので自らの歩みを少し振り返ってみたい。入学以降、ドクターまで過ごした名古屋大学で学位を取得した後、運よく前任校の北海道大学に職を得ることができた。といっても国の地震予知計画の一翼を担う部署であったため、座して行う研究だけでなく、野外の地震観測や地殻変動観測が大きな比重を占めた。しかし、私を含めて予知事業に携わる研究者たちが、阪神・淡路大震災を引き起こした1995(平成7)年兵庫県南部地震を予知できなかったことが社会の強烈な批判を呼び、地震予知計画は根底から見直しがはかられることになった。この頃から私は次なるステップを模索し始めた。防災を意識した地震・津波に関連するシミュレーション系の研究にも本腰を入れ始めた。
そうこうするうちに愛媛大学の地球科学教室に異動することになった。着任したのは2005(平成17)年4月のことであった。ちょうど理学部が3学科から5学科に改組されたタイミングである。北国とは趣の異なる理学部の佇まいを前に、身の引き締まる思いであった。地球科学科で始まった新しい生活はすべてが新鮮だった。それまで『地球物理』という専門の枠からそれほど離れた経験がなかったため、教室の談話会で聴く地質、岩石・鉱物、古生物等の専門的な話には学生時代に戻ったような感覚を味わった。また、教育(野外実習)として野外調査を行うことの難しさをあらためて感じた。在職2年目からは学科長を任されることになった。それ以降、諸般の事情もあって、結局5年間を学科長として過ごした。前任校では学生との付き合いが少なかったため、教室運営の中で学生に関連する事柄には特に気を配った。今風に言えば学生ファーストである。
5年間の学科長生活の後、定年までの7年間を副学部長として過ごした。定年直前の最後の2年間は評議員を拝命し、大学運営のありようを肌で感じることになった。後から見れば、在籍した13年間のうち12年間は学科・学部の管理運営に携わったことになる。とりわけ後半は、FD(Faculty Development)委員会、入試検討委員会、理学部全体の通信インフラ維持管理などが主なミッションであった。『我々は研究のプロであって教育のプロではない』と某先生に言われたことがあるが、理学部のFDをとりまとめることになった時にはそうも言っていられないと感じた。教育企画室の先生方に相談し、効果が薄いFD行事をとりやめ、実効性のあるものをとりいれた。委員会の統廃合後は理学部・理工学研究科(理学系)の入口(入試)に関するとりまとめ役となった。一言一句に正確性が要求され、実施に際してもミスが許されない入試という性質上、緊張感が途切れないように気を遣った。これに比べると通信インフラの維持管理はやや気楽であった。1990年頃のインターネット黎明期よりサーバ運営の経験があったため、それほど大きな抵抗は感じなかった。余談になるがネット黎明期の前後は、VAX/VMS、NEWS-OS、SunOS などを使いわけていたが、1990年代前半以降は、現在に至るまで、研究や仕事に使うOSはLinuxである(この原稿もLinux+Emacsで書いている)。
一方、それまで物理探査や地下構造解析が主な研究分野であったが、2011(平成23)年東北地方太平洋沖地震(3.11地震)による未曾有の災害発生以降は、かねてよりすすめていた津波シミュレーションや地震による応力変化といった防災・減災に焦点をあてた研究が中心となった。幸い、ソフトウェアの開発はいわば自家薬籠中であり、 解析に必要な理論を組み合わせてそれを実装する計算ツールをほぼすべて自作した。将来の発生が予想される東南海・南海地震による津波シミュレーションの結果、四国の太平洋沿岸では、3.11地震と同サイズ・同すべり量の断層運動を仮定すると最大で17メートル、さらにすべり量を倍程度にすると30メートルを超える津波が短時間でやってくることがわかった。その後、研究室の学生たちと一緒になって、日本を取り囲むほぼすべての沿岸地域での津波波高想定を求めた。手元に溜まった計算結果を整理する前に定年で時間切れになってしまったので、今後は徒然なるままにまとめてみたいと考えている。また、長い間温めてきた地球物理の教科書執筆のアイディアがなんとか形になり、時間切れになる前に刊行にこぎつけることができたのは幸運だった(この教科書は2014年に朝倉書店より出版された)。
振り返ってみれば、土地も人も温和な愛媛・松山の懐に飛び込んで過ごした13年間は、あっという間に過ぎ去った一炊の夢であった。これからは気儘に時間を使って研究を継続し、夢の続きを見るつもりである。最後になりましたが、在職中にお世話になった皆様にはこの場を借りて御礼申し上げます。ありがとうございました。皆様の益々のご健勝とご多幸をお祈りするとともに、1学科制となる新しい理学部の発展を心より祈念いたします。


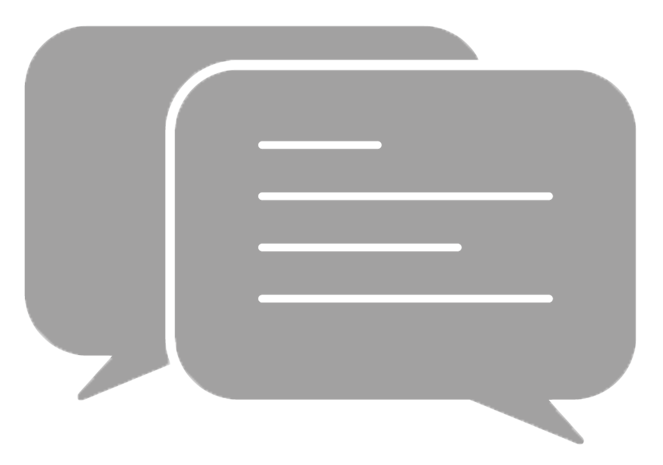 物理
物理