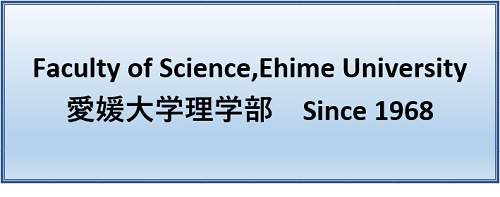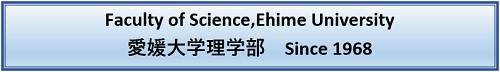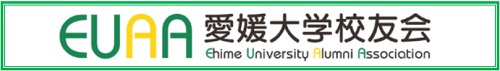母校の窓>2014
2014年度・2013年度末退職の先生方からのメッセージ
退職にあたって
内藤 学
 平成27年3月に定年退職を迎えるにあたって思い出等を書くよう依頼されました。しかし、私は元来の筆無精、文章書きは嫌いなので困惑しましたが、とにかく何か書いてみます。
平成27年3月に定年退職を迎えるにあたって思い出等を書くよう依頼されました。しかし、私は元来の筆無精、文章書きは嫌いなので困惑しましたが、とにかく何か書いてみます。
私は平成7年4月に教授として赴任して以来愛媛大学理学部に20年間勤めさせていただきました。赴任した頃は全国の国立大学で教養部の廃止・教養部教員の他学部への分属などの色々な大学組織改革が行われていました。愛媛大学では平成7年度をもって教養部が廃止になり、それに伴って理学部では翌年度からの学部の学科再編、博士後期課程(理学系)の設置等がありました。私は赴任後まだ1年でしたが数理科学科の最初の学科長を務めました。その際、先輩の教授や多くの先生方のご指導・ご協力を戴きました。当時の教員の方々にあらためて感謝する次第です。
その頃、大学の会議や講義・セミナーの合間に気分転換をするためによく理学部キャンパス内の小さな林を散歩しました。(今は、その場所に総合研究棟が建っています。講義棟の東側にはテニスコートもありました。)それにしても、愛媛大学は自然環境に恵まれた処にあります。護国神社、一草庵、御幸寺山麓の寺々…と散策するのも気持ちの良いものでした。
私が理学部数学科(あるいは、数理科学科)の20年間で指導教員として担当したのは、結局(見込みを含んで)、学部生70名、マスター学生15名、ドクター学位取得学生2名でした。数学を多くの若者と一緒に勉強できたことは大変幸せでした。これら学生には(もちろん、理学部の全卒業生、全在学生にも)愛媛大学理学部で学んだことに自信と誇りをもって日々過ごして戴きたい。
私の研究分野は解析学、とくに“実領域における常微分方程式論”です。これまで40年間ずっと2階あるいは高階の常微分方程式の解の振動的性質と漸近的性質について研究してきました。常微分方程式論は使う道具立てが少ないので、逆に、研究が難しいこともあるのですが、幸いなことに解決したい問題は涸渇することなく、どうにか論文を書き続けることができました。「隣の花は赤い」と言って、人のやっている研究は面白く華々しく見えましたが、私にとっては、同じテーマで研究してきたことが良かったようです。しかし、最近の(とくに、若い)研究者には色々な分野に興味をもって研究を進めて欲しいと思います。
退職後も、細々とではありますが、やはり常微分方程式の研究を続けていきたいと思います。数学は極論すれば一人で自宅の居間で研究できますし、今後は趣味としての数学ですから、のんびりと気楽にやっていきます。
以上、取り留めのない文章になりましたがお許しください。
愛媛大学でお会いした多くの学生、教員、職員の皆様に親しくご交誼いただいたこと深く感謝しております。末筆になりましたが、皆様方の益々のご発展とご健康を心からお祈り申し上げます。
退職に関して思うこと
柏 太郎
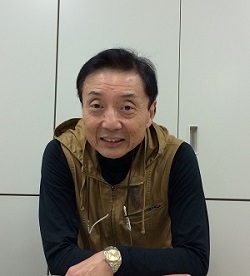
名古屋大学で博士論文を書きあげた当時は、職のないオーバードクターの時代(今より厳しかった。ポスドクは国内ではほとんど皆無。外国に行くほかなかった)。アメリカで6年間ポスドクを死ぬ気でやって、だめだったらあっさりやめて別のことを(はっきりと何をやるか決めていたわけではないが)やるつもりで、素粒子奨学生として京都大学基礎物理学研究所で1年間、筑波の高エネルギー物理学研究所でさらに半年間過ごした。幸運にも九州大学理学部に職を得ることが出来たときは、妻と二人で万歳三唱したものだった。 職を得てからは35年あまりの研究・教育生活である。助手・助教授時代は楽しくて仕方なかった。昼過ぎに大学に行って、大学院生と議論しては、年に1、2本の論文を書いて、毎晩のように、時には朝まで酒を酌み交わした。カナダに長期滞在した折には、友人のカナダ人に『うらやましいな太郎は。気分転換やストレス解消が普通は必要なのに、趣味が仕事になっているから。』と言われたときは、実感はなかったが、後に痛いほどこの言葉が心に突き刺さることになる。
愛媛大学に着任した2002(平成14)年には、大学法人化の具体化が問題となり始めており、理学部では教育改革が始まっていた。赴任挨拶の後、当時の柳沢学部長、野倉評議員と学部長室での雑談の折、カリキュラムの話題になった。直前に九大で物理のカリキュラム改革をやってきたばかりなので、あれこれ経験談をぶっていると突然、『これからの理学部も教育改革正念場なので、手伝ってくれ』と言われた。これが全ての始まりであった。理学部発祥の教育コーディネーターの統括をやることになり、(すべて同じ時期に)学部長補佐、評議員、統括研究コーディネーター・経営政策室などと研究・教育以外の仕事に忙殺されるようになった。何もかもが、法人化に伴う初めてのことで誰も経験がない。学長・評議会メンバー・学部長・補佐室メンバーで話しあいながら進むほかなかった。必然的に多くの時間を費やすこととなる。方針は、ある程度トップダウンで出すしかないが、教育に関しては、文科省の顔色をうかがいながらのものは特に評判が悪い。ストレスはたまる一方である。日曜日は本当に、マルクス・エンゲルスの言葉じゃないが『労働力の再生産過程』であった。こんな生活のなか、松山に呼び寄せた母も94歳の生涯を閉じていった。父も、ここで亡くなっているので、松山は父母の死所と言うことになる。
忙しい中でも、研究との接点は単行本(演習場の量子論:サイエンス社・量子場を学ぶための場の解析力学:講談社・演習繰り込み群:サイエンス社)や事典(大辞林・新物理学小事典:三省堂)などの執筆でかろうじて保っていたが、数年前からは法人化後の施策もようやく安定化してきて、前例にならう仕事が定着してきたことで、少しずつ自分の時間が増えてきた。特に最後の3年間は、理学部執行部の若返りもあって、研究・教育中心の生活に戻ることが出来、10年ぶりに論文を書き、新たな単行本2冊の執筆に費やす十分な時間を持てることになった(経路積分に関するものは2015年秋に裳華房から、相対性理論に関するものは、数学書房から出版される)。
退職後はカナダのオカナガン地方のペンティンクトンという町でのんびり過ごすのが夢であったが、現実はなかなか厳しく、しばらくは本の執筆と、(非常勤での)講義のブラッシュアップなどの仕事を続けることになりそうだ。週に10万歩を目標に、体力を維持しながら、時には山登りでもしようと思っている。
最後になったが、これからも理学部という特質を、つまり、すぐには結果の出ない基礎研究を強力にサポートする体質を、前面に出した愛媛大学理学部であることを切望して、筆を置きたい。
長い間、お世話になりました。これからもよろしくお願いします。
はるか昔を振り返って
皆川 鉄雄
 私が東雲小学生のころの楽しみの一つに、愛媛大学城北キャンパスの原っぱでの虫とりがありました。キャンパスはかつての練兵場(軍の演習場)跡地に設立されたのですが、昭和30年ごろの大学には今のような施設はほとんどなくキャンパスの北西一帯には草原が広がっており、学校帰りにここに立ち寄る多くの小学生がいました。塾通いする子供もほとんどいなくて、帰り道に立ち寄り、また日曜の長い1日を過ごすこともありました。
私が東雲小学生のころの楽しみの一つに、愛媛大学城北キャンパスの原っぱでの虫とりがありました。キャンパスはかつての練兵場(軍の演習場)跡地に設立されたのですが、昭和30年ごろの大学には今のような施設はほとんどなくキャンパスの北西一帯には草原が広がっており、学校帰りにここに立ち寄る多くの小学生がいました。塾通いする子供もほとんどいなくて、帰り道に立ち寄り、また日曜の長い1日を過ごすこともありました。
当時の男子大学生の多くは今と異なり、学生服の上着(ただし女性の服装の記憶はありません)を着ており、またかなりの学生が大學のマークの入った学生帽を被っていたと記憶しています。御幸中学校(現東中学校)時代は、理学部の前身である文理学部のキャンパスを訪れるのが楽しみでした。木造校舎の1階には後の地球科学科教授になられた地学教室の宮久研究室があったのですが、建物の中には入ったことはありませんでした。昭和43年愛媛大学農学部農芸化学科に入学し、卒論研究は土壌肥料学教室を希望しました。土壌肥料学教室には船引真吾教授、吉永長則助教授、電顕が専門の山口助手がおられました。船引先生は、日本で初めてX線粉末回折法を用いて土壌中の粘土鉱物の同定を行った先生であり、吉永先生はイモゴと呼ばれる火山灰から新しい粘土鉱物「イモゴライト」を発見された火山灰粘土鉱物学の第一人者でした。研究室は九州大学と肩を並べる日本を代表する土壌学研究室として知られていました。当然研究設備も充実しておりXRD(加熱装置付)、IR, TG-DTA, TEM, 化学分析装置など粘土鉱物を研究する上で必要な分析機器が全て揃っていました。
吉永先生の研究指導を受けましたが、いまでも思い出すのが、厳しく指導されたガラス器具の洗浄方法と毎日の実験台の拭き掃除です。洗ったあとガラス器具に水滴が残っていると、駄目だしがありました。また朝、昼、夜と実験台の上を拭くことが日課でした。今では考えられないことですが、当時の実験室の天井はアスベストがむきだしの状態であり、ごくまれに実験台上に落ちてくることがあったのです。卒業後は、2年間の聴講生を経た後、土壌肥料学教室の技官として就職しました。吉永先生の指導のもとイモゴライト研究の他に、フィールドワーク、住友化学との共同研究である稲のポット試験等の多くの雑用をやっていましたが、自由な時間もあり、休みにはテントを担いで日本各地の山を駆け巡っていました。研究時間の合間には好きだった鉱物の検討も吉永先生の許しを得て行っていました。鉱物に関して分からないことがあれば、理学部の宮久研究室にお邪魔して教えを請いました。時には九州の金属鉱床、特に金、銀、錫鉱床の調査に同行させていただいたことも多々あります。串木野鉱山、赤石鉱山、岩戸鉱山、豊栄鉱山などの調査はほんとうに楽しい思い出です。宮久先生の名前を出すとどこの鉱山もフリーパスでした。とんでもない先生だったことをいまさらながら感じています。
ある時、築地書館から「四国地方鉱物採集の旅」の執筆依頼があったのですが、一緒にやりませんかと声をかけて頂きました。二つ返事でお引き受けし、四国の鉱物産地をめぐる日が続きました。出版までに2年ぐらいかかったのですが、その間の夜おそくまでの打ち合わせも楽しい思い出です。
しばらくたって理学部に新しく地球科学科が誕生することが決定し、技官の定員がついたので来ませんかとのお誘いがありました。それまで私自身、鉱物には興味がありましたが、地球科学科の職員になることなどまったく考えていませんでした。おまけに、そのお誘いは街の本屋でばったりお会いした時でした。あの時お会いしなかったら、今は無かったかもしれません。吉永先生に相談したところ研究室としては困るが、君自身は理学部に移ったほうが良いというお言葉を頂き、理学部に移ることを決心しました。地球科学科技官として先生方の薄片作成、X線装置の修理、学生実験の手伝い、フィールド調査や、学会用のスライド作成などの雑用すべてやりました。その後縁あって助手になってからは、桃井斉先生の研究室に所属し、マンガン鉱物の検討を主テーマにし現在に至っています。その間、1年間、北海道大学の針谷研究室にお世話になったのですが、研究そっちのけで北海道の林道を走り回り、鉱物採集に明け暮れていました。また毎週技官の方とお酒を酌み交わしていたことも懐かしい思い出です。
愛媛大学に入学し愛媛大学で停年を向かえ、今やっと卒業するような気分です。まだまだ老け込む年ではないと思ってはいるのですが、いつまで思えるかあやしいものです。ただこれからも新しい鉱物の発見・研究に少しでも係わることができればと願っています。幸いなことに私の研究室を出た多くの石好きの学生と現在も交流があり、また研究者として活躍されている方もおられます。もう少しは頑張ってみようと思っています。
吉永長則先生、桃井斉先生、宮久三千年先生、針谷宥先生をはじめ、多くの先生方にはほんとうにお世話になりました。また事務の方々にもたいへんお世話になりました、心から感謝いたします。
恩師の思い出
佐藤 成一
愛媛大学には37年間お世話になり昨年無事に定年を迎えました。この間、いろいろなことがあり過ぎて何を書けばよいのかわかりませんが、お世話になった方々、なかでも、愛媛大学に赴任するきっかけをつくってくれた大学時代の2人の恩師のことが真っ先に浮かんできます。学部及び修士課程でご指導いただいた広島大学理学部の田中隆荘先生と大学院博士課程でお世話になった京都大学原子炉実験所の石田政弘先生についての思い出話を紹介して挨拶に代えさせて頂きます。
私が田中先生にお世話になったのは、先生が「日本産菊の起源と進化のしくみ」を明らかにされた下斗米直昌先生の研究室を引き継ぎ、教授になられて間もない頃でした。ご専門は細胞遺伝学で、植物の核型分析や育種学に大きな足跡を残されています。特に、ラン科植物の分類・進化の研究で知られています。先生は、どんな学生でも辛抱強く慈愛に満ちた態度で接し、失敗を責めるようなことは一切しませんでした。私にも幾つか思い出に残る失敗談があります。当時昆虫採集が趣味の一つであった私は、沖縄に一度でいいから行ってみたいと常々思っていました。そんな折、私が修士課程に進学した昭和47年5月15日に沖縄が日本に返還されました。好都合なことに事務手続きで遅配されていた奨学金が6月に3カ月分まとめて手に入りました。そしてすぐ夏休みです。これは沖縄に行くまたとない絶好のチャンスです。私は夏休みに乗じて教員には何も告げず、一週間ほど沖縄全土をめぐり県の天然記念物のコノハチョウ以外の沖縄に生息している全種類の蝶を採集して大満足で大学に帰ってきました。直後に、田中先生から呼び出しを受け、「貰えない人がいるのにそんなふうに奨学金を使うのはどうだろう」と諭されたことがあります。しかし、穏やかでゆっくりした口調でかすかに笑みを浮かべながらお話になるので素直な気持ちで聞くことができました。もう一つ思い出に残る失敗があります。研究室共同で使用しているカメラをうっかり開けてしまい、中に入っていたフィルムを感光させてしまったのです。それを見ていた助手の方が血相を変えて近づいてきて、田中先生のところに行くから一緒に来いということでついて行きました。にこにこしながら仔細を聞いていた先生は、カメラの中に使用中のフィルムが入っていることが分かるようにしておかなかったのが悪いのではないかと逆に助手の方を諌め、私をかばってくれたのです。先生は当たり前のことを言っただけだったかもしれませんが、この時の経験がその後学生を指導する上で多少生かされた様な気がします。
博士課程に進学すると同時に、田中先生の勧めがあって大阪府熊取町にある京都大学原子炉実験所で2年間お世話になりました。そこには、当時、田中先生と懇意にしていた石田政弘先生が葉緑体DNAに関する研究をしておられました。私も、葉緑体DNAの合成に関する研究していましたので、お世話になることになったのです。石田先生は、米国コロンビア大学のSagerの研究室で葉緑体DNAを発見し、京都大学に戻ってきて間もない新進気鋭の研究者でした。そのお人柄は4文字熟語で表現すると、豪放磊落、才気渙発そして天真爛漫といった言葉で形容され、気さくで自由な雰囲気をもっておられました。その言動はしらふでも冗談と本気が区別できないほどで、お酒が入るとさらにエスカレートし、話の真偽の境界が全く分からなくなり、周りを惑わせることがよくありました。例えば、「自分は石田三成の子孫である」から始まり、「若い時には北海道を独立させる夢をもっていた。若い者はそれ位大きな夢をもたなあかん」といったような話がどんどんでてくるわけです。半分あきれながらも、おもしろいので適当に相槌を打ちながら話を合わせるわけです。ただ、石田先生の実家は数百年前に建てられた立派なお屋敷で祖先が2万石の大名であったという噂がありましたので、石田三成とつながりがあるという話はまんざら嘘ではなかったかもしれません。先生は、とても学識が広く、そしてなにより発想がユニークで、話を聞いていて飽きることがありませんでした。ところが、研究の指導は直接することは一切ありませんでした。矢継ぎ早に、いろいろなアイデアを出すが、決してこうしなさいとは言いません。あくまで何をやるかは自由でした。これは、愛媛大学に赴任後、一人で研究しなければならなくなった時、大変役に立ちました。
昭和51年に愛媛大学に採用が決まった時、先生がはなむけにくれた言葉が「佐藤君、愛媛に行ったら、一旗揚げんとあかんぞ。」でした。その後、この言葉は研究に行き詰った時の励みとなりました。愛媛大学に赴任時に、設備と研究費の関係で研究テーマを変更せざるを得なくなり、考えあぐねた末、核小体について顕微鏡を使った研究をすることにしました。理由は、葉緑体リボソームRNAに関する研究をしていたので、同じリボソームRNAを含む核小体に興味があったことと、何よりもあまり関心を持つ人がいなかったので、競争やお金を気にせずに研究できそうだったことです。いろいろ苦労がありましたが、当時ほとんど解明されていなかった核小体の構造についてかなりすっきりと理解できる程度の成果をまとめることができました。
大学時代にこのように大きな影響を与えてくれた先生方と巡り合えることができたことを大変幸運に思っています。田中先生の研究に対する真摯な姿勢と慈愛に満ちた指導そして石田先生の自由な発想と研究の厳しさ、励ましの言葉は、迷いや困難に遭遇した時に私を教育研究生活の原点に立たせてくれました。田中先生は、その後広島大学の学長、そして広島市立大学の初代学長になり両大学の教育研究の改革や運営に尽力されました。そして、平成20年に82歳で永眠されました。石田先生は、平成12年に亨年73才の若さでお亡くなりになりました。永眠されたお顔は十分人生を楽しんだのか、大変安らかで「佐藤君、ムシロ旗でも揚げることができたかね」といわれそうな気がしました。先生の名は、国際エンドサイトバイオロジー学会が設置したミーシャー・石田賞に刻まれ、その功績が称えられています。補足ですが、理学部の施設や教育研究の環境は今や素晴らしく整備され、私が赴任した当時とは隔世の感があります。最後に、理学部の今後の教育研究の益々の発展と卒業生の皆さんのご活躍を祈念しております。
理学部の思い出
村井 佳名子
私は、平成10~12年度の3年間及び平成23~25年度の3年間の計6年間を理学部でお世話になり、平成26年3月末に定年を迎えました。 大好きな理学部で二度も勤められたこと、そして定年を迎えることができたことを、とてもありがたく幸せに思っています。
 最初に理学部に配属された時に驚いたのは、先生同士がさん付けで呼びあっていらっしゃることでした。それまで所属していた学部では、上位職の先生に対しては「○○先生」と呼ぶのが当然のことでした。最初は驚きましたが、理学部に慣れるにつれ、理学部の自由度の大きさを示す一つの例なのかな、と思うようになりました。理学部は城北地区にありながら、他の学部と道路を隔てた立地の故か、独特の空気が流れているキャンパスでした。南国を思わせる木が並び立つロータリー、憩いの森と称される緑の空間が何とも魅力的でした。事務職員と先生方との距離も近く、事前に各人の活躍度を予想した出走表なるものが配られる理学部ボウリング大会など、折々に楽しい行事もありました。 平成11年4月に、事務組織の集中化で職員数が半減し、しばらくは混乱を極めましたが、そこはチームワークのよい理学部のこと、先生方のご協力(と、事務職員の頑張り!)によって、いつの間にか落ち着いていたものでした。
最初に理学部に配属された時に驚いたのは、先生同士がさん付けで呼びあっていらっしゃることでした。それまで所属していた学部では、上位職の先生に対しては「○○先生」と呼ぶのが当然のことでした。最初は驚きましたが、理学部に慣れるにつれ、理学部の自由度の大きさを示す一つの例なのかな、と思うようになりました。理学部は城北地区にありながら、他の学部と道路を隔てた立地の故か、独特の空気が流れているキャンパスでした。南国を思わせる木が並び立つロータリー、憩いの森と称される緑の空間が何とも魅力的でした。事務職員と先生方との距離も近く、事前に各人の活躍度を予想した出走表なるものが配られる理学部ボウリング大会など、折々に楽しい行事もありました。 平成11年4月に、事務組織の集中化で職員数が半減し、しばらくは混乱を極めましたが、そこはチームワークのよい理学部のこと、先生方のご協力(と、事務職員の頑張り!)によって、いつの間にか落ち着いていたものでした。
二度目に配属された時には、大好きだった憩いの森をはじめ、温室やテニスコートが姿を消して、キャンパスの景色が変わっていたことに少々寂しさを感じましたが、理学部の温かさは変わらぬままでした。ある先生から、「おかえりなさい」と声をかけていただいた時の嬉しさは、今も忘れられません。また、5学科に戻されたり、入試制度や学生支援等々、教育システムや教育環境の整備に力を入れられて、他学部に率先して新たな仕組みを取り入れられていること、各研究センターが大きく発展されていることが、とても印象的に映りました。
その後の3年間はまたたく間に過ぎ、今は大学から離れた生活を送っていますが、辞めた後も特に気になりますのが、デマンド問題です。改修工事に伴う省エネ化によって、”理学部の暑く長い夏”が少しでも緩和されんことを切に願っています。 最後に、あらためまして理学部の皆様方に心からのお礼を申し上げますとともに、理学部及び理学同窓会のますますのご発展をお祈り申し上げます。


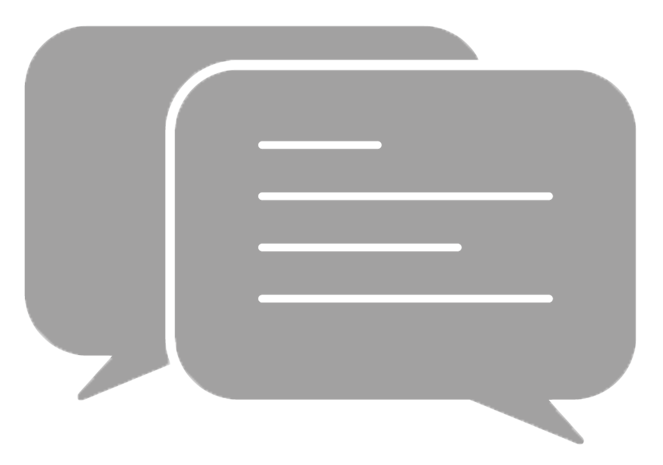 数学教室
数学教室