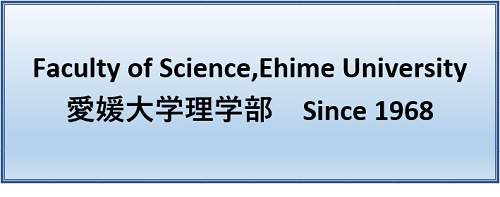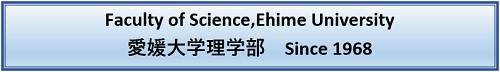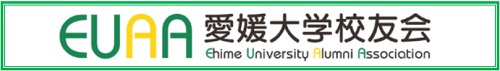母校の窓>2012
2012年度・2011年度末退職の先生方からのメッセージ
長いこと夢をみていた
森本 宏明
仙台から本学に赴任して、27年の歳月が夢のように過ぎました。定年にあたり、自らの辿って来た道を振り返ってみることにします。
 2000年に待ち望んでいた短期留学が年齢制限の最終年になって認められました。まず、若い頃75年にアメリカでお世話になった加藤先生にお目にかかって挨拶をしなくてはとUC Berkeleyから出発を開始するつもりでした。当時、ペーペーの実績も何もない突然現れた青二才を快く受け入れてくれ親切にしてくれました。休日には車で1時間ほどのNapa Valleyへ連れて行ってくれてWineryでWineを御馳走になり、ぶどう畑に座って奥さんと3人でおにぎりを頂きました。大勢の弟子に囲まれて数学の議論をしている様子を見るにつけ、世界の一流人は流石に凡人とは違うと感動を受けました。今年ブームの龍馬さんが勝先生の弟子になったときに、きっと同じ思いだったに違いありません。しかし、残念な事情があってお目にかかることが叶わなくなり、生涯の心残りとなっています。
2000年に待ち望んでいた短期留学が年齢制限の最終年になって認められました。まず、若い頃75年にアメリカでお世話になった加藤先生にお目にかかって挨拶をしなくてはとUC Berkeleyから出発を開始するつもりでした。当時、ペーペーの実績も何もない突然現れた青二才を快く受け入れてくれ親切にしてくれました。休日には車で1時間ほどのNapa Valleyへ連れて行ってくれてWineryでWineを御馳走になり、ぶどう畑に座って奥さんと3人でおにぎりを頂きました。大勢の弟子に囲まれて数学の議論をしている様子を見るにつけ、世界の一流人は流石に凡人とは違うと感動を受けました。今年ブームの龍馬さんが勝先生の弟子になったときに、きっと同じ思いだったに違いありません。しかし、残念な事情があってお目にかかることが叶わなくなり、生涯の心残りとなっています。
計画はNew YorkとParisの大学に1ヶ月ずつ滞在することにしました。セミナーや研究会に参加する他は観光めぐりです。地下鉄で列車を間違えて途方にくれたり、ひったくりに会いそうになったり、山の中で大嵐にあったり、片言のフランス語が通じたりと、様々な冒険のおまけ付きです。遊んでばかりいたようにも見えますが、そうではありません。外国の空気を吸うことは研究の肥やしとなり、新鮮な気分と漲る活力を生み出してくれます。
帰国後、一念発起して世界中で使われる本を書くことにしました。自分の老化に抵抗しながら、薪に臥す様にして完成までに4年を費やしました。次に出版社の用意したreferee達から承諾を得る手筈になります。Referee reportsを待ったり、原稿を読んでないのが分かって反論したりして、胆を嘗める思いで3年。最終的にCambridge大学出版から好意的な受理の通知を受け、それから出版までに1年掛かりました。Internetで調べると、出版社の恥にならないぐらいは普及していて、一安心です。仙台の知人からは、「よくやった。そんな発想は南の人だからできるのよ、北の方の人には思い浮かばないね」と賛辞を頂戴しました。あっそうだったのか、道は違っても龍馬さんと同じ夢を見ていたのだと、思い至りました。子供の頃、遠足で桂浜へ行ったときには、「この銅像の人は、どうした人なが」、「”りゅうま”と書いちゅうにどうして”りょうま”と呼ぶが、間違ごうちゃあせんかえ」、とずっと思っていました。あなたの倍近く生きてきて、挫折の辛さや成功の歓びを知りました。あなたの夢が志半ばで断たれた無念さに涙し、同じ土佐の血が流れていたことを誇らしく思います。今度京都へ行ったら、お墓参り致します。
研究は確率微分方程式(精密になったLangevin方程式でSDEと略記)で記述される経済モデルのシステムを最適化することに焦点があります。企業の資本がBlack-Scholes SDEで表され時間の増加関数として投資量を決定する場合、得られる利潤から投資量を差し引いた純利益のtotal期待額を最大にするにはどうすれば良いでしょうか。資本金が或るしきい値A以下の企業にはリスク回避にため投資をしません。資本がAを越えているときには、資本がAに達したときだけ適切な量を投入するのが最適政策で目的を達する事ができます。勿論、Aの存在や投入量について解析はできますが、実用化のためには数値計算が必要です。
この研究は端緒に着いたばかりで、これで隠居という訳にはいきません。テーマを発展させ、纏まった本として出版できたら無上の喜びとなるでしょう。
脳天気な極楽オヤジ
大六 隆
先日,理学同窓会から会報第7号の発行に際して「寄稿依頼」という身に余る有り難いお話をいただいた。幼少の頃よりずっと学業については全く熱心でない上に読書することも希なことも手伝って,文章作りが苦手なため,一度は辞退させていただく旨のお返事をしたものの,このような機会は一生に二度とないことに鑑み,恥を忍んで同窓会のご厚意に甘えさせて頂くこととした。
 “脳天気な極楽オヤジ”これが,僕がこの世で最も敬愛する妻の「夫評価」である。夫婦なんだから…もう少し気の利いた評価をもらえないものかとも考えるが,そんなことを言おうものなら,「アンタはいいよネェ~!お気楽で…」とのお小言を頂戴した後に「男はツマラン!!」と、持ち前の九州訛りで一撃必殺の怒りの鉄拳をお見舞いされることとなる。いずれにしても,世界中の誰よりも長い時間を僕と共に過ごしている「相方」の実体験に基づく偽わらざる評価なのだから,甘んじて受け入れなければなるまい。その実僕は,八幡浜市の山奥の小さな山村で農家の長男として産声を上げて以来,良きにつけ悪しきにつけ…何かに悩み苦しんだという記憶がとんと無い。
“脳天気な極楽オヤジ”これが,僕がこの世で最も敬愛する妻の「夫評価」である。夫婦なんだから…もう少し気の利いた評価をもらえないものかとも考えるが,そんなことを言おうものなら,「アンタはいいよネェ~!お気楽で…」とのお小言を頂戴した後に「男はツマラン!!」と、持ち前の九州訛りで一撃必殺の怒りの鉄拳をお見舞いされることとなる。いずれにしても,世界中の誰よりも長い時間を僕と共に過ごしている「相方」の実体験に基づく偽わらざる評価なのだから,甘んじて受け入れなければなるまい。その実僕は,八幡浜市の山奥の小さな山村で農家の長男として産声を上げて以来,良きにつけ悪しきにつけ…何かに悩み苦しんだという記憶がとんと無い。
学業の修得が優先されてしかるべき時期の,幼少期から小学,中学,高校,更には大学に至るまでも,あまり好きではなく苦手な勉学に真正面から取り組むことから逃げ,気の合う仲間達とスポーツや遊びを通じて楽しく時を過ごしてきた。特に,高校時代には,当時八幡浜高校陸上競技部の顧問をされていた兵頭寛先生(後に本学教育学部教授,名誉教授)に厳しくご指導いただき,しっかりとした基礎体力を養成していただき,3年生時には1600mリレーのメンバーとしてインターハイにも出場することができた。また,大学時代には,入学早々に体育会合氣道部に入部し,3回生時から主将となったこともあり,勉学そっちのけの学生生活に更に拍車がかかった。そんな僕の大学生活の状況を称して両親曰く,「お前は,体育学部合氣道学科に入学したのか!。」と…。でも,その時の仲間達は,僕の一生の“宝物”であり,それよりも何よりも…生涯の伴侶と出会ったのもまた部活動を通じてであった。
幸いなことに,このようなスポーツや遊びに興ずる“お気楽生活”は,大学職員となってからも続けることができており,我が家に帰り着くなりユニフォームに着替えてグローブを片手に慌ただしくナイターの試合(3チームに所属しているため,シーズン中はほぼ連日)に出かけようとする僕の目をじっと見つめて,可愛い孫娘から「ネェ・ジイジ,ジイジの本当のお仕事はヤキューなの…?!」と、問われる始末。(孫娘の後で,妻と娘がザマ~ミロ!と言わんばかりにニヤリ…)
1951年2月生まれのため,会報が発行される頃には既に還暦を過ぎているはずの僕は,「この歳」になってもまだ,やがて訪れる「死」に至るまでに成し遂げたり継続していたい“夢”や“目標”が一杯ある。
・60cmオーバーのグレを釣り上げること
・70歳になるまで少なくとも1年に1本はフルマラソンを完走すること
・70歳になるまで東温市代表のソフトボールチームの一員としてプレーし続けること
・四国八十八カ所の歩き遍路を成就すること
・田舎で一人気丈に暮らし続けている母にそっと寄り添い,優しく見守ること
そして何よりも…永年に亘りこんな“脳天気な極楽オヤジ”を温かく支え続けてくれた妻と共に仲良く平穏で心豊かに悠々と時を過ごすこと・・・これらの“夢”や“目標”を実現するため,これからも両親から授けてもらった有り難くも丈夫な我が身のメンテナンスを怠ることなく,一日々を大切にして,“明るく”“楽しく”そして“いさぎよく”生き抜いていきたいと考えている。
末筆ながら,これまで出会いお世話になった皆様方に改めて御礼を申し上げると共に,皆様方の今後益々のご健勝とご活躍,理学同窓会の更なるご発展を心よりお祈り申し上げます。
合 掌
恩師
真鍋 敬
 退職してから,これまでのことを振り返る機会が多くなりましたが,やはり一番思い出すのは大きな影響を受けた先生方のことです。今治市の日吉小学校5年生のとき,素晴らしい担任の先生(故矢野高宣先生)に出会うことができ,学校での毎日が楽しくなりました。社会科や算数の授業などいくつかの場面が,黒板の前に立つ若々しい(当時30歳くらいでしょうか)先生のお顔とともに思い出されます。父が松山で教員をしていた関係で,6年生の2学期から愛媛大学近くの清水小学校に転校しました。
退職してから,これまでのことを振り返る機会が多くなりましたが,やはり一番思い出すのは大きな影響を受けた先生方のことです。今治市の日吉小学校5年生のとき,素晴らしい担任の先生(故矢野高宣先生)に出会うことができ,学校での毎日が楽しくなりました。社会科や算数の授業などいくつかの場面が,黒板の前に立つ若々しい(当時30歳くらいでしょうか)先生のお顔とともに思い出されます。父が松山で教員をしていた関係で,6年生の2学期から愛媛大学近くの清水小学校に転校しました。
高校を卒業して大学生になってみると,ほとんどの先生,特に教授は近付き難い存在で,授業も一方的で学生は人間扱いされていないような感じでした。今から思うと,あのころ起きた大学紛争は政治的な問題だけでなく,このような状態に対する学生の不満が背景にあったように思います。大学院生会の委員として教授会とやり合ったり,「大学解体」を叫ぶ学生グループへの反対デモに参加したりして,博士課程1年から2年にかけては実験どころではなく,先の見えない毎日でした。それを見かねた当時京都大学理学部化学科助教授の故廣海啓太郎先生に,酵素反応速度にかかわる研究テーマをいただき,懇切なご指導のもとで何とか4年で博士論文を書き上げることができました。
大学院生時代の不行跡から,大学の職につくのは難しいと覚悟していたのですが,幸運にも30歳で東京都立大学(当時)理学部化学科の奥山典生教授の研究室に助手として採用されました。奥山先生との連日の討論から,研究テーマは独創的であるか,実験計画に妥協はないか,など研究に対する厳しい姿勢を学び,7-8年後にはもうお互いに話をしなくても考えていることがわかるようになりました。都立大学に15年余り勤めたあと,新設された姫路工業大学理学部(当時)の寺部 茂教授の研究室に助教授として採用され4年過ごしました。ある日,私が大学院生のころに研究室の助手をしておられた六鹿宗治先生からお電話を頂き,「愛媛大学の理学部化学科で公募をしているぞ,そろそろ親孝行をしたらどうや」とのこと,締め切りまで一週間ほどしかなく大急ぎで資料を整えて応募したところ,また幸運にも採用されました。一人っ子の私が松山に戻ったことをことのほか喜んでくれた父は,着任後1年と4ヶ月足らずで亡くなりました。
この公募当時学科長であられた河野博之教授には,私が研究を始めやすいように理学部本館2階の数部屋を空けて用意して頂いただけでなく,それらの部屋の壁のペンキ塗りまでして頂きました。ペンキの塗りあとは芸予地震後の耐震改修工事でなくなりましたが,河野先生とは理学部と中国清華大学理学院との交流協定の締結のための北京訪問などでおつきあいを頂き,その篤実なお人柄と科学に対する献身には,お会いするたびに感服します。
東京で大学の教員になった時は,まさか毎日の通勤の行き帰りに母の住む実家や卒業した小学校の前を通ることができるようになるとは思っていませんでした。このような幸運を得たのも,また教えることや研究することの楽しさを35年にわたって感じ続けることができたのも,お名前をあげさせて頂いた先生方をはじめ多くの恩師のおかげです。この場を借りて深く御礼申し上げます。


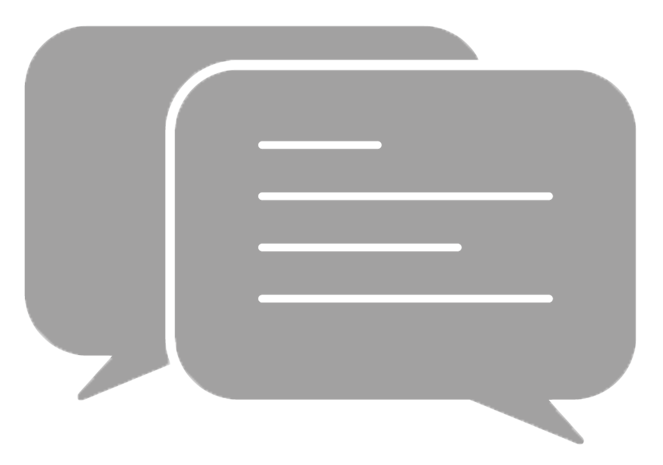 数学教室
数学教室