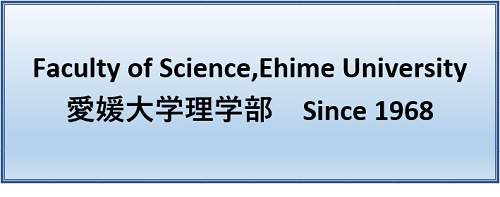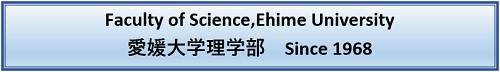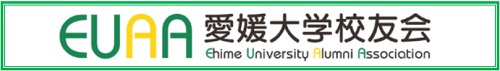母校の窓>2010
柳沢康信学長からのメッセージ
2009年3月退職の先生方からのメッセージ
愛媛大学のビジュアル・アイデンティティについて
愛媛大学長 柳澤 康信
 昨年9月4日,理学同窓会総会において「愛媛大学の近況あれこれ」と題して,教育,研究,社会連携などの取組みに関して1時間あまり話をする機会がありました。そのあとの懇親会で,「このごろ愛媛大学はよく頑張っているね」とか「新聞やテレビで愛媛大学の活躍を知る機会が多くてうれしい」などお褒めの声を頂戴しました。このような声はわれわれ現役の教職員にとってうれしい限りであり,力強い励ましになります。
昨年9月4日,理学同窓会総会において「愛媛大学の近況あれこれ」と題して,教育,研究,社会連携などの取組みに関して1時間あまり話をする機会がありました。そのあとの懇親会で,「このごろ愛媛大学はよく頑張っているね」とか「新聞やテレビで愛媛大学の活躍を知る機会が多くてうれしい」などお褒めの声を頂戴しました。このような声はわれわれ現役の教職員にとってうれしい限りであり,力強い励ましになります。 さて,この小稿の表題をビジュアル・アイデンティティ (visual identity)としましたが,皆さんはこの言葉をご存知でしょうか。この言葉は「企業や商品のイメージを統一して,書体やマークなど視覚的なものによって,そのイメージを表現すること」という意味で,具体的にはブランドマーク,ロゴタイプ,マスコットキャラクターなどを指します。企業がこれらを重視するのは当然のことですが,近頃ではイメージアップを図るために国公私を問わず多くの大学が制定するようになっています。
さて,この小稿の表題をビジュアル・アイデンティティ (visual identity)としましたが,皆さんはこの言葉をご存知でしょうか。この言葉は「企業や商品のイメージを統一して,書体やマークなど視覚的なものによって,そのイメージを表現すること」という意味で,具体的にはブランドマーク,ロゴタイプ,マスコットキャラクターなどを指します。企業がこれらを重視するのは当然のことですが,近頃ではイメージアップを図るために国公私を問わず多くの大学が制定するようになっています。
愛媛大学でも遅蒔きながら,平成21年の開学60周年を記念して制定することになりました。ネットを通じて公募したところ 708作品もの応募があり,その中から私が委員長を務める選考委員会が選んだのが文中の図です。 ブランドマークは円と「e」を組み合わせたシンプルな形ですが,「愛媛の知の拠点(ドット・エヒメ)」となる決意を込めています。円は太陽,「e」は躍動する姿,そして全体の形はすこやかに伸びていく新芽の象徴です。また,色彩は愛媛みかんをイメージした黄色で,明朗さ・快活さを表しています。
 マスコットキャラクターは,「e」と愛媛みかんを組み合わせたものです。これもシンプルな形ですが,おっとりとした愛媛の気風を映した穏やかな表情が持ち味で,「遠くをみつめる澄んだまなざしと穏やかな表情は,純粋で素朴な若者の豊かな将来性を示している」という意味づけをしています。愛称は「えみか」。これも愛媛とみかんの組み合わせで,ほほえみを浮かべたキャラクターに似つかわしい名前になっています。
マスコットキャラクターは,「e」と愛媛みかんを組み合わせたものです。これもシンプルな形ですが,おっとりとした愛媛の気風を映した穏やかな表情が持ち味で,「遠くをみつめる澄んだまなざしと穏やかな表情は,純粋で素朴な若者の豊かな将来性を示している」という意味づけをしています。愛称は「えみか」。これも愛媛とみかんの組み合わせで,ほほえみを浮かべたキャラクターに似つかわしい名前になっています。
ブランドマークの制作者は兵庫県に在住のグラフィックデザイナー福原基和さん,マスコットキャラクターのほうは長野県の主婦,宮川さやかさん。福原さんには平成21年11月11日に行った開学60周年記念式典に出席していただいて,そこで表彰状と副賞を差し上げました。驚いたのは,本学の沿岸環境科学研究センターと地球深部ダイナミクス研究センターの馴染みのブランドマークが彼の作品だったこと。これは沿岸環境科学研究センター長の武岡さんがたまたま福原さんの知り合いであったことによる由。これらの縁で福原さんにはその後,新調した身分証明書,封筒,名刺,それからポロシャツなどの大学グッズのデザインまでお願いしています。
マスコットキャラクター「えみか」はこの1年間で学生・教職員の間でかなり認知されるようになり,人気も上がっているようです。昨年4月,城北キャンパス正門の北側に南加記念ホール,校友会館,愛大ショップの3つの建物を整備しましたが,そのうち愛大ショップの名称は「えみか」としました。このショップでは,附属農場産の安心米や特別支援学校の生徒が制作した木工品,地元の酒造会社の協力を得て作った特別純米酒「媛の酒」,ブランドマークを模したロールケーキなどのオリジナル商品を販売しています。そのショップの前に「えみか人形」を設置しました。この人形は1時間に1回,体を左右に回転しながら学歌を演奏し,夜間には内側から光るようになっています。本学は「地域に開かれた大学」を目指していますが,「えみか人形」もそのための雰囲気づくりに一役買っています。
各大学はブランドイメージを向上させるために,あれやこれやの手を打っています。しかし,「大学ブランド」はなかなかの曲者です。日本では,ブランドイメージは創立の古さや伝統によって固定化しており,容易に変化しません。もちろん,ブランドイメージを向上させるためには,教育・研究など大学の本来的な使命を充実させることが一番です。しかし,これまで国立大学が実力の割に十分な評価を得てこなかったのも事実です。その理由として,宣伝不足が挙げられます。ビジュアル・アイデンティティの制定などイメージアップのための総合的な広報戦略が今日求められていると感じています。
定年となります”その随想
井上直樹
 思えば長く教員生活をいたしました。大学、大学院を修了して大学の付置研究所に採用され、そこで約10年、その後愛大約27年です。付置研時代は、学生、院生も少なく研究室は静かでしたが、愛大に赴任したときはまことに新鮮でありました。大学内は若さが溢れ、サークル活動の声が響き、教室は活気に満ちていました。赴任してまもなく御幸会館の大広間でたてコンがありそのにぎわいと親密さには感動しました。物理学科の大集団でした。ここにいる学生達もいろいろな思いで、物理学を専攻しているのだろうなという思いで酒を飲んでいましたが、ふと自分はどうだったのかと振り返っていました。最初に科学に興味を覚えたのは、小学生のときに父親がつれてくれた研究所の見学でした。いまでもその感動を思い出しますが、その後は、数式があり、論理的に考えるところなどがおもしろそうで物理を選びました。最近、理学部でも科学大好き子供達を集めた親子で楽しむ科学実験を開いていますが、私も少しお世話しましたが、子供への影響は大きく、これは大切な催し物と思います。私は10~20代のころは科学にしか興味がありませんでした。政治や経済、芸術などの分野は、今は大変おもしろいと思っています。一度、きちんと本を読んで、法律や経済、哲学などを専攻した友人と、なぜ若くしてそのような分野を選んだのかなど、一度ゆっくりと酒でも飲みながら話してみたいと思っています。
思えば長く教員生活をいたしました。大学、大学院を修了して大学の付置研究所に採用され、そこで約10年、その後愛大約27年です。付置研時代は、学生、院生も少なく研究室は静かでしたが、愛大に赴任したときはまことに新鮮でありました。大学内は若さが溢れ、サークル活動の声が響き、教室は活気に満ちていました。赴任してまもなく御幸会館の大広間でたてコンがありそのにぎわいと親密さには感動しました。物理学科の大集団でした。ここにいる学生達もいろいろな思いで、物理学を専攻しているのだろうなという思いで酒を飲んでいましたが、ふと自分はどうだったのかと振り返っていました。最初に科学に興味を覚えたのは、小学生のときに父親がつれてくれた研究所の見学でした。いまでもその感動を思い出しますが、その後は、数式があり、論理的に考えるところなどがおもしろそうで物理を選びました。最近、理学部でも科学大好き子供達を集めた親子で楽しむ科学実験を開いていますが、私も少しお世話しましたが、子供への影響は大きく、これは大切な催し物と思います。私は10~20代のころは科学にしか興味がありませんでした。政治や経済、芸術などの分野は、今は大変おもしろいと思っています。一度、きちんと本を読んで、法律や経済、哲学などを専攻した友人と、なぜ若くしてそのような分野を選んだのかなど、一度ゆっくりと酒でも飲みながら話してみたいと思っています。
大学の教員をしてよかったなと思うことを三つほどあげてみます。やはり学生を世に送り出すことができた。これが一番です。卒業後に再会したときなどは、その成長ぶりを目の当たりにしますと感動です。二番目は、いや限りなく一番に近いですが、学生、院生と共に研究できたことです。成果を学生達と学会で発表したり、国際会議にでかけたりしますと我々の意欲が上がります。国内外に友人もできました。これらはまことにすばらしい。平成18年度から理学部卒論発表会を公開でできるようになったことも、よいことです。三つ目は夢を持ち続けることができたことです。若い学生達と毎日接しているからでしょうか、先生は元気だとよく言われました。かなり前ですが、ある学生が“大学の先生みたいになりたい”と言ってきました。どうして?“先生方の顔をみていると、いつも夢をもちながら歩んでいる姿がいい”でした。“夢”! いい響きですね。確かに大学での研究は果てしない夢を追いかけている面があります。改めてこの気持ちをいつも忘れないようにしてきました。
 このごろの大学は、いろいろと忙しく、大変窮屈になってきました。諸般の事情で、このようになっているのは十分理解できます。しかし、大学に効率一辺倒はなじまない。教育や基礎研究は時間がかかります。律することは必要だけれども、自由で夢のある大学でありたいものです。最近はデジタル化も進み電子メールは便利だけれど、なんだか味気ない。意志の疎通もあまりよくない。形式的になり人間性にも影響しているように見えます。もっと感性が豊かになるようなアナログの部分がほしいものです。実験なんぞ見てみましても、装置が故障するとデジタルの部分は手の出しようがない。その点、物理の基本となる手作りに近い実験装置は、テスターとシンクロスコープ、機械の異常音、目視、ハンダ付け、機械工作などで直せますので、快適です。まさにアナログの世界バンザイです。理学部には10年ほど前までは、テニスコートや卓球台があり、多くの教職員と学生で忙しい合間をぬっては運動していました。みんなが健康的でよかった。今のキャンパスにも何らかの運動施設やベンチなどで休憩できる小公園、もっと牧歌的な雰囲気がほしいですね。
このごろの大学は、いろいろと忙しく、大変窮屈になってきました。諸般の事情で、このようになっているのは十分理解できます。しかし、大学に効率一辺倒はなじまない。教育や基礎研究は時間がかかります。律することは必要だけれども、自由で夢のある大学でありたいものです。最近はデジタル化も進み電子メールは便利だけれど、なんだか味気ない。意志の疎通もあまりよくない。形式的になり人間性にも影響しているように見えます。もっと感性が豊かになるようなアナログの部分がほしいものです。実験なんぞ見てみましても、装置が故障するとデジタルの部分は手の出しようがない。その点、物理の基本となる手作りに近い実験装置は、テスターとシンクロスコープ、機械の異常音、目視、ハンダ付け、機械工作などで直せますので、快適です。まさにアナログの世界バンザイです。理学部には10年ほど前までは、テニスコートや卓球台があり、多くの教職員と学生で忙しい合間をぬっては運動していました。みんなが健康的でよかった。今のキャンパスにも何らかの運動施設やベンチなどで休憩できる小公園、もっと牧歌的な雰囲気がほしいですね。
昭和57年からお世話できた卒論生、大学院生の総数は数えてみますと114名にもなりました。学生達の研究は、キーワードでいいますと、超音波緩和、ブリルアン散乱、レーザーブラッグ反射、分子振動緩和、臨界現象、ナトリウムイオン伝導、混合アルカリ効果、リチウムイオン伝導、非アレニウス型イオン伝導、微粒子分散、電子状態など多数にのぼります。この間、アメリカで1年、ドイツで2ヶ月研究もさせてもらいました。教育では講義はもちろんですが、研究室ゼミナールが楽しかった。その他、ソフトボール大会、テニス大会、ボーリング大会、バーベキュー、花見、飲み会などなど質素だけれど充実したものでした。これらのことができたのも共に歩んだ学生達のおかげです。この場を借りまして卒業生みなさんにお礼を申し上げます。今後は、残りの研究データの整理と計算、共同研究および国際学術誌のエデイタをもう少し続ける予定です。写真を2枚のせました。写真1は1987年のソフトボール大会です。写真2は今年度最後の卒論生、修論生および私です。
最後に、卒業生皆様の今後のご健勝とご活躍、また理学部および理学同窓会の発展を願いまして終わりにしたいと思います。
計算尺からパソコンへ
東 長雄
 昭和41年、私は愛媛大学文理学部理学科に入学しました。鉄鋼メーカに5年近く勤めた後の入学でしたので、角帽を購入するなど、当時の大学生のトレンドからワン-テンポ遅れていた記憶があります。学部卒業後の大学院生活では愛媛大学を離れましたが、博士課程修了と同時に旧教養部に赴任し、以来愛媛大学を離れることなく、34年間教員を続けさて頂き、来る3月末で定年退職となります。その間にお世話になった方々にまず御礼を申し上げ、ご迷惑をお掛けした方々に心からお詫びを申し上げます。
昭和41年、私は愛媛大学文理学部理学科に入学しました。鉄鋼メーカに5年近く勤めた後の入学でしたので、角帽を購入するなど、当時の大学生のトレンドからワン-テンポ遅れていた記憶があります。学部卒業後の大学院生活では愛媛大学を離れましたが、博士課程修了と同時に旧教養部に赴任し、以来愛媛大学を離れることなく、34年間教員を続けさて頂き、来る3月末で定年退職となります。その間にお世話になった方々にまず御礼を申し上げ、ご迷惑をお掛けした方々に心からお詫びを申し上げます。
学部での想い出の持ち物に計算尺があります。化学計算用と使用目的は限られていました。有効桁数に不足はないものの、位取りは暗算で行わねばならず、その点では不便でした。しかし、お陰で概算練習を毎回していたことになります。
大学院に進学して紙テープ入力式、その後、紙カード入力式の電子計算機及び電卓の使用により位取りが不要となり、概算が下手になったと思います。パソコンに至っては、計算よりも文書作成に多く使うようになり、楽ができました。しかし、読めても漢字を書けない、送り仮名を多く間違う、入力に慎重さを欠くなど、高能率・便利さと引き替えに失ったものも多いと感じています。
効率と能率は似て非なるものと思います。単純に云えば、効率は仕事量(成果)と投入エネルギー(資材)の比です。効率が悪ければ社会及び自然環境への負荷を大きくします。効率的行動とは、合理的な行動と云えましょう。能率は仕事量と所要時間の比です。ことさらに能率を追求すれば、効率が低下する可能性が大です。有限の寿命しか持たないヒトにとって、効率と能率のバランスこそが肝要であることは云うまでもないことです。
過度な利益及び利便性の追求とは「効率にではなく能率に重点を起き過ぎる」考え方ではないでしょうか。生存の必須条件である食糧生産すら国際的な分業体制でよしとする考えは、その線上にあると云えないでしょうか。人類の稲作の開闢は小麦とほぼ同時期の6千年昔に遡り、日本での稲作も2~3千年前に始まったとされます。既に数千回も主要穀物の生産が更新・継続されてきました。日本は資源小国とよく云われますが、その資源とは耐用年数が二百年にも満たない更新性ゼロの地下資源を主として指しています。更新可能な資源である農林水産資源及び(資源といえば語弊がありますが)人的資源をもっともっと大切にする国であって欲しいと願います。
人的資源育成を目的とする本学で40年近くを過ごせたことは、本当に有り難いことと思います。しかし、効率ではなく能率を追求し過ぎてきた我を思う近頃でもあります。せめて退職後は、効率に重点を置く、むしろスロー-テンポな生活をと想う今日この頃です。
最後になりましたが、理学同窓会員の皆様方のご健勝を心よりお祈り申し上げます。
退職に際しての感想等
愛媛大学理学部事務課長
長谷川 広武
 私は、今年度で愛媛大学を定年退職することになりますが、遠山先生から理学同窓会報(第6号)を発行するので退職に当たり、何か原稿を書いてほしいとの依頼を受けました。私自身、同窓会の会員でなかったため、少し躊躇しましたが、「退職に際しての感想等」で良いということでしたので、普段から思っていることや感じていることなどを書かせていただきました。
私は、今年度で愛媛大学を定年退職することになりますが、遠山先生から理学同窓会報(第6号)を発行するので退職に当たり、何か原稿を書いてほしいとの依頼を受けました。私自身、同窓会の会員でなかったため、少し躊躇しましたが、「退職に際しての感想等」で良いということでしたので、普段から思っていることや感じていることなどを書かせていただきました。
「子年」生まれの私は、今年で5巡目の年男となり、還暦を迎えました。気持ちはいつまでも若いつもりでしたが、身体の方は確実に年を取っているようです。以前は、体を動かすことが好きで、いろいろなスポーツをしてきましたが、10数年前から頑固な腰痛に悩まされ、長い間、体を動かすのに不自由を感じておりました。でも、この年になると今の身体に対し、良く動いているなあと、感謝の気持ちが持てるようになりました。あるできごとから、歩ける間にできるだけ歩こうと決心して、3年前から毎朝4キロ程度を「日々新たに」と「感謝」の気持ちを持ちながら歩いています。今では、松山から東京間を十分往復できる距離まで歩き続けることができています。
話は変わりますが、国立大学は、平成16年度から、百年に一度あるかないかの大改革と言われている独立法人化の制度が導入されました。今の時代にあっては、避けて通ることのできないことかもしれませんが、市場原理が取り入れられたこの制度は、基礎科学を対象とする分野にとって大変厳しいものとなっています。近い将来、この制度が大幅に修正されなければ、本当に大切な分野が衰退し、我が国は没落していくように思います。
また、今の日本は、成果のみが重視され、結果よければ全てよしとの感が強く、プロセスを大切にされないことや地道に努力をする者が格好悪いものとして軽んじられる傾向にあります。これらのことが、現在の閉塞感や行き詰まり感を強くしている大きな原因ではないかと思います。このような中にあって、基礎基本を重視し、土台のしっかりした、奥行きがあり、応用力のある人材の育成を目的としている理学教育は、将来、社会の流れを大きく変えていく力を持っているように感じます。
それから、今年は本当に嬉しいことがありました。日本人がノーベル賞を4人も受賞し、それも全て基礎分野の科学者でした。これを契機に、この分野の重要性が早く再認識されることを期待しております。
とりとめのないことを書きましたが、基礎分野がますます発展することを心待ちしているうちの一人です。


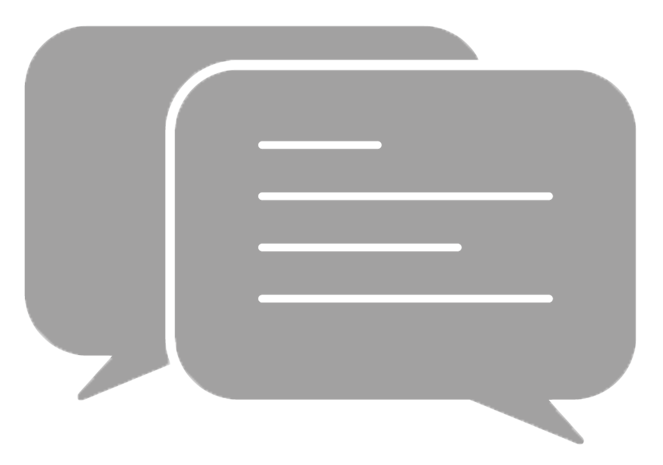 愛媛大学長
愛媛大学長