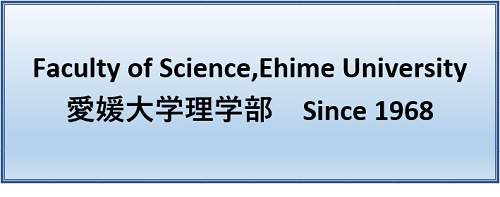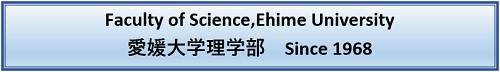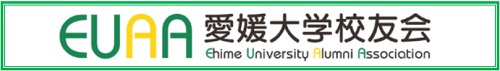母校の窓>2008
向井 和男 先生からのメッセージ
2007年年度末退職の先生方からのメッセージ
抗加齢(アンチエイジング)とビタミン・サプリメント
愛媛大学名誉教授 向井和男
 理学同窓会会長の城尾昌範先生の依頼により、9月20日(土)に開催された理学部同窓会の総会の前に、表題のようなタイトルで講演させて頂きました。同窓会の総会の開催は平成11年以来とのことで久し振りでしたが、私の予想を遥かに超える70数名の参加者があり、改めて旧制松山高等学校と文理学部を母体とする理学部の伝統を感じました。
理学同窓会会長の城尾昌範先生の依頼により、9月20日(土)に開催された理学部同窓会の総会の前に、表題のようなタイトルで講演させて頂きました。同窓会の総会の開催は平成11年以来とのことで久し振りでしたが、私の予想を遥かに超える70数名の参加者があり、改めて旧制松山高等学校と文理学部を母体とする理学部の伝統を感じました。
ビタミンA 、C、Eやユビキノン-10、ポリフェノール類などの抗酸化剤を含むサプリメントは世に溢れていますが、種々の広告やテレビ番組ではその効用の科学的根拠は殆ど述べられていません。私の専門が化学で、また、受講者が化学の基本が分かる理学部の出身者であることを考え、講演ではサプリメントの効用の基となる分子構造と活性の相関に関する基礎的な説明を行いました。夜の懇親会では、化学科の卒業生を始め、多くの卒業生の方々と楽しいひと時を過ごすことが出来ました。
 私が所属した化学科構造化学講座は、理学部が発足した1968年にスタートし、石津和彦先生を初代の教授とし、現在に至っています。その間、研究室からは約350名の学生諸君が卒業して行きました。昨年は、石津先生の叙勲と言う嬉しいニュースがあり、お祝いの会を開きました。その際分かったのですが、研究室の卒業生の内、女性4名を含む24名が博士号を取得していました。これは、理学部の卒業生の優秀さと、卒業後の皆様の活躍の一端を示す嬉しい事実です。
私が所属した化学科構造化学講座は、理学部が発足した1968年にスタートし、石津和彦先生を初代の教授とし、現在に至っています。その間、研究室からは約350名の学生諸君が卒業して行きました。昨年は、石津先生の叙勲と言う嬉しいニュースがあり、お祝いの会を開きました。その際分かったのですが、研究室の卒業生の内、女性4名を含む24名が博士号を取得していました。これは、理学部の卒業生の優秀さと、卒業後の皆様の活躍の一端を示す嬉しい事実です。
ご存知のように、ここ数年間続いた好景気も、米国発の不況の波が押し寄せ、当分は学生達の就職戦線は厳しいものとなることが予想されます。私も現役時代には就職をお世話する機会が多かったのですが、その際、民間企業で活躍されている卒業生の人達に助けられたことが度々ありました。景気が良い時は問題ないのですが、不況の際に頼りになるのは、やはり多くの先輩が就職し、活躍している企業です。今後も卒業生諸君が種々の分野で活躍し、その結果として、現役学生の卒業後の道が開かれると言う、良循環が続くことを願っています。
尚、私こと、理学部化学科を3年前に定年退職し、現在も民間企業などとの共同研究のために、理学部本館5階の研究室で研究を続けています。松山にお越しの節は気軽に声をお掛け下さい。
愛媛大学での思い出
理学部物理学科
菅谷礼爾
 大学院を修了後、愛媛大学理学部の電磁物理学研究室の助手として松山市に来ました。故野本尚敬教授の放電物理学の研究室で、私の専門のプラズマ物理学と近い分野です。放電物理学の実験装置はありましたが、プラズマ物理学の実験装置は皆無でしたので殆どゼロからの出発でした。幸い核融合の研究に多くの研究予算が配分された時期でしたので、2~3年で実験装置を作ることが出来て何とか研究を始められました。実験による研究を10年程続けた後、観測された現象を説明する理論を発展させる事が出来、理論的研究に徐々にシフトしてゆき現在に至っています。この当時、名古屋大学のプラズマ研究所(現在の核融合科学研究所)の大型計算機が無料で使用出来たので理論的研究を進展させられました。又、愛媛大学の計算機センター(現在のメディアセンター)を利用させて頂き感謝しております。
大学院を修了後、愛媛大学理学部の電磁物理学研究室の助手として松山市に来ました。故野本尚敬教授の放電物理学の研究室で、私の専門のプラズマ物理学と近い分野です。放電物理学の実験装置はありましたが、プラズマ物理学の実験装置は皆無でしたので殆どゼロからの出発でした。幸い核融合の研究に多くの研究予算が配分された時期でしたので、2~3年で実験装置を作ることが出来て何とか研究を始められました。実験による研究を10年程続けた後、観測された現象を説明する理論を発展させる事が出来、理論的研究に徐々にシフトしてゆき現在に至っています。この当時、名古屋大学のプラズマ研究所(現在の核融合科学研究所)の大型計算機が無料で使用出来たので理論的研究を進展させられました。又、愛媛大学の計算機センター(現在のメディアセンター)を利用させて頂き感謝しております。
磁化プラズマ中の非線形波動現象の研究で、空芯磁場コイルによる強い磁場中に真空装置を置きその中にプラズマを作って実験を行います。卒業研究や院生の特別研究でのこの実験や計算機による理論研究においてはとても活気があり多くの思い出があります。実験やゼミの終了後、研究室で酒を飲みに行くなど研究以外でも活気があったと思います。 この中の思い出の1つが大山スキー場に行った事です。
1977年度の卒業研究では5名の卒論生を私と須川先生で指導しプラズマ実験を精力的に行いましたが、それ以外にスキーというスポーツの指導も行いました。休日を利用して、美川スキー場や鳥取県の大山スキー場に民宿宿泊で行きましたが私と須川先生と他研究室の1名の4回生以外全員スキーが始めての経験です。不思議な事に教官による理論指導のお陰で短期間で全員スキーが上達し1名の学生は私よりも上手になったのには驚きました。私のスキーの資格が2級ですので1級のレベルに達した事になります。1級はスキーの指導員になれる資格です。大山のスキー場には私と卒論生が運転する乗用車2台で行き、スキー場の駐車場に乗用車を置いてゲレンデのすぐ近くの斜面にある民宿に宿泊しました。私は先頭の乗用車に後れないように懸命に運転した記憶があります。帰る時に大雪のため乗用車は1m以上の積雪に完全に埋まり、「松山に帰れない」、「明日の授業に間に合わない」とパニック状態になりましたが、全員で除雪を行い何とか出発できる状態にしました。しかし、私の乗用車のバッテリーが低温で使用不能になりエンジンが始動できません。近くのガソリンスタンドで新品のバッテリーに取替えてやっと出発に至りました。大山から米子市に向かって出発したとたんに、タイヤにチェインを取付けてられているにもかかわらず今度は乗用車のスリップが起こり、私が先頭で運転する事になりました。私は雪国生まれなので雪道の運転はよく分かります。このようにして翌日の授業に間に合い、卒論生の授業に対する真剣な態度は、「教官にスキーで勝った、野球で勝った、車の運転で勝った」と言っていた事や、大山の頂上から見える日本海の景色と共に忘れられない思い出です。その後も大山スキー場に何回か行きましたが2度と乗用車では行きませんでした。夜行列車で行って同じ民宿宿泊です。
この時から30年の歳月が過ぎましたが、それぞれ社会で活躍している事と思います。教育研究と公私共に充実した38年を過ごさせていただいた愛媛大学と卒業生に感謝しています。
思い出など
江沢康生
私が着任したのは、有名な松山商業と三沢高校の決勝戦があった、昭和44 年でした。当時は宿直室があり、そこのテレビは予選のときから松山商業の試合のときは、多くの人が集まりました。秋になると愛媛大学にもいわゆる大学紛争が伝わってきました。事務局が、翌春には法文舘が占拠されたことはご記憶の方も多いと思います。私たちも学生と泊まり込んだり、教養部講義棟などの出入り口に待機したりして、警戒に当たりました。
間もなく、紛争は終わり、文理改組後の教育・研究が軌道に乗るようになりました。授業では演習をいくつか担当していましたので、大抵の学生の顔と名前が一致し、よく付き合いました。中でも、昭和49年に3回生と新歓ソフトボール大会に参加し、出場98 チーム(メンバーの1 人が覚えていました) で準優勝したのが記憶に残っています。その後、昭和53年に教養部に移りましたが、理学部のときとは逆に講義ばかりで受講生も約50 人と多く対象の学科も大抵毎年変わりました。顔と名前が一致するのは高々7 割台といったところでした。
その後、平成に入り、教養部の改組が近づく頃から、理学部の学生の卒論、修論の指導を非公式ながら担当し、改組に備えました。改組後は、もちろん公式に指導を担当しましたが、そのころの研究テーマは後述のようにすでに重力理論・宇宙物理に移っていてました。これらのテーマに興味を持つ学生は優秀で、修論にわずかに手を入れれば、journal 版になりました。
研究は、紛争後、素粒子論研究者でグループを作りました。このグループは様々な変遷をたどりましたが、私は素粒子の統一理論との関連で、宇宙物理にも興味を持つようになりました。宇宙の主要な力はもちろん重力で一般相対論で記述されてきましたが、近年では、弦理論の影響もあり、その一般化に興味が持たれています。また時空も5 次元以上の場合が研究の対象になっています。そういうわけで、近頃は「多次元高階重力理論」の理論構造やその応用を研究テーマにしています。
燃焼反応経路を求めて37年
樋高 義昭
 博士課程3年生の5月で退学し、昭和46年6月、愛媛大学理学部助手に採用頂き、37年目を迎えた本年3月31日に退職いたしました。思い出して見ますと、昭和46年4月、須賀先生(当時愛媛大学理学部化学科教授)より、私の恩師である山村先生に、“燃焼反応を一緒に研究出来る者を探している”との電話があったそうで、先生に勧められ、愛媛大学を訪問・見学しました。これを機に、37年間、理学部で過ごす事となりました。その当時、衝撃波管は気相高温反応の研究にとって理想的な反応測定装置と云われ、日本のいろんな研究機関で導入を計画されていましたが、衝撃波管装置一式を外注すると1千万円近くの費用が必要と云われ、簡単に導入出来る時代ではありませんでした。しかし、須賀先生の計らいで、衝撃波管装置を使用しての燃焼研究を始める事になり、赴任と同時に設計と材料探しに明け暮れる毎日を過ごしました。須賀先生の人脈の広さと私の愛用車、ホンダ“N360”の行動力で、昭和48年には衝撃波管装置の第一基目をほぼ完成することができ、最初に手掛けた研究が、エチレンの燃焼反応特性の研究であります。更に、運のいいことに、十数年に一度回ってくる理学部の特別予算で、四重極質量分析計を高温高速反応の研究に応用する研究(二基目の衝撃波管装置)を始める事が出来き、1974年には日本では初めてそれに成功する事ができました。その後、その装置を炭化水素の燃焼反応研究に応用し、他の方法では測定困難な、酸素分子の高速時間挙動を明らかにする事も出来ましたし、この装置の開発・成功は、化石燃料を含むCH化合物燃料の燃焼反応の基礎である、アセチレン燃焼反応機構構築(1996年に正逆反応を合わせて、約206個の素反応からなる反応機構を発表)の根幹をなす結果ともなりました。昭和53年には、これら一連の研究が認められ、新制の大学教官としては、初めて、吉田科学技術財団の助成を受け、渡米する機会を得ました。当時の高温反応機構の世界的研究者である、米国、テキサス大学オースチン校のガーディナー教授のもとで1年半、低級炭化水素であるC1,C2炭化水素(メタン、エタン、エチレン、アセチレン)の研究を行い、世界の他の研究室に先駆け、CH化合物燃料(化石燃料を含む)の基礎となるC1,C2炭化水素の燃焼反応機構を発表することが出来ました。このテキサス大学オースチン校での研究を通して、高温反応機構の計算手法を学び、その後の燃焼反応機構研究の発展の基礎を作ることが出来ました。帰国後、相次いで燃焼反応機構の懸案であったホルムアルデヒド、ケテン、アセチレン、エチレン、エタン、メタンの研究を手掛ける事ができました。本研究室で開発作製した3基の特色ある衝撃波管と、コンピュ-タを駆使し、独自の燃焼反応機構研究システムを用いて、系統的に、C8までの炭化水素燃料、更にエーテル、アルコール、フロン類等を研究する事ができました。地方大学では、無理と云われた研究を37年間と云う長きに渡り続けてこれましたのは、ひとえに須賀先生を始めとする先輩の先生方、愛媛大学文理学部・理学部の卒業生の皆様のお陰と深く感謝いたしております。この場を借りまして厚くお礼申しあげます。
博士課程3年生の5月で退学し、昭和46年6月、愛媛大学理学部助手に採用頂き、37年目を迎えた本年3月31日に退職いたしました。思い出して見ますと、昭和46年4月、須賀先生(当時愛媛大学理学部化学科教授)より、私の恩師である山村先生に、“燃焼反応を一緒に研究出来る者を探している”との電話があったそうで、先生に勧められ、愛媛大学を訪問・見学しました。これを機に、37年間、理学部で過ごす事となりました。その当時、衝撃波管は気相高温反応の研究にとって理想的な反応測定装置と云われ、日本のいろんな研究機関で導入を計画されていましたが、衝撃波管装置一式を外注すると1千万円近くの費用が必要と云われ、簡単に導入出来る時代ではありませんでした。しかし、須賀先生の計らいで、衝撃波管装置を使用しての燃焼研究を始める事になり、赴任と同時に設計と材料探しに明け暮れる毎日を過ごしました。須賀先生の人脈の広さと私の愛用車、ホンダ“N360”の行動力で、昭和48年には衝撃波管装置の第一基目をほぼ完成することができ、最初に手掛けた研究が、エチレンの燃焼反応特性の研究であります。更に、運のいいことに、十数年に一度回ってくる理学部の特別予算で、四重極質量分析計を高温高速反応の研究に応用する研究(二基目の衝撃波管装置)を始める事が出来き、1974年には日本では初めてそれに成功する事ができました。その後、その装置を炭化水素の燃焼反応研究に応用し、他の方法では測定困難な、酸素分子の高速時間挙動を明らかにする事も出来ましたし、この装置の開発・成功は、化石燃料を含むCH化合物燃料の燃焼反応の基礎である、アセチレン燃焼反応機構構築(1996年に正逆反応を合わせて、約206個の素反応からなる反応機構を発表)の根幹をなす結果ともなりました。昭和53年には、これら一連の研究が認められ、新制の大学教官としては、初めて、吉田科学技術財団の助成を受け、渡米する機会を得ました。当時の高温反応機構の世界的研究者である、米国、テキサス大学オースチン校のガーディナー教授のもとで1年半、低級炭化水素であるC1,C2炭化水素(メタン、エタン、エチレン、アセチレン)の研究を行い、世界の他の研究室に先駆け、CH化合物燃料(化石燃料を含む)の基礎となるC1,C2炭化水素の燃焼反応機構を発表することが出来ました。このテキサス大学オースチン校での研究を通して、高温反応機構の計算手法を学び、その後の燃焼反応機構研究の発展の基礎を作ることが出来ました。帰国後、相次いで燃焼反応機構の懸案であったホルムアルデヒド、ケテン、アセチレン、エチレン、エタン、メタンの研究を手掛ける事ができました。本研究室で開発作製した3基の特色ある衝撃波管と、コンピュ-タを駆使し、独自の燃焼反応機構研究システムを用いて、系統的に、C8までの炭化水素燃料、更にエーテル、アルコール、フロン類等を研究する事ができました。地方大学では、無理と云われた研究を37年間と云う長きに渡り続けてこれましたのは、ひとえに須賀先生を始めとする先輩の先生方、愛媛大学文理学部・理学部の卒業生の皆様のお陰と深く感謝いたしております。この場を借りまして厚くお礼申しあげます。
松山で過ごした18年
小野 昇
 平成2年4月から、18年の間、愛媛大学理学部で有機化学の教育・研究に従事し、平成20年3月31日に無事に定年で退職しました。学生、教員、職員、近所の飲食店で会った人達の暖かさに助けられて、楽しい18年が送れたことを感謝しています。この18年での一番の思い出は、非常に多くの学生を指導して、社会に送り出したことです。有機系の先生と学生とが、3月9日に最終講義と記念の同窓会を開催してくれましたが、在校生も含めると150人を超す人が集まって、私の定年を祝ってくれました。そのとき、愛媛大学で18年を過ごせた幸せを実感しました。
平成2年4月から、18年の間、愛媛大学理学部で有機化学の教育・研究に従事し、平成20年3月31日に無事に定年で退職しました。学生、教員、職員、近所の飲食店で会った人達の暖かさに助けられて、楽しい18年が送れたことを感謝しています。この18年での一番の思い出は、非常に多くの学生を指導して、社会に送り出したことです。有機系の先生と学生とが、3月9日に最終講義と記念の同窓会を開催してくれましたが、在校生も含めると150人を超す人が集まって、私の定年を祝ってくれました。そのとき、愛媛大学で18年を過ごせた幸せを実感しました。
愛媛大学に赴任するまでは、研究が中心の生活でしたが、松山に来て以後は、この町ののんびりした空気にそまり、多くの学生とのんびりと研究を楽しみました。しかし、この環境の中で、ここでしかできない研究をしようと秘めた野望ももっていました。私の専門は有機合成です。有機合成が対象とする研究課題は多彩です。例えば、医薬品の製造では、生理活性物質を見つけ、その候補の分子を効率よく合成するためには、有機合成が重要です。私は松山に来るまでは、このような有機合成の手法の開発研究をしていました。松山では、有機分子の電子機能の開発研究をしました。通常は絶縁体の有機分子が半導体や導電体に変化することにロマンを感じました。定年間際になって、真空を使わないでフタロシアニンのような顔料の薄膜を塗布で作成することに成功しました。この技術を応用すると大面積の有機薄膜太陽電池の製造とか有機EL素子のインクジェットを利用した作成などが可能になります。実際、これらの試験的な試みは、三菱化学の研究所で成功していますが、これらが商品化されるころには、きっと私はこの世にいないでしょう。幸いにも、もう少しだけこの研究に関わることができることになりましたので、時々松山に来ます。そして、道後の湯につかったあと鰺の刺身とビールを楽しむ予定です。
京都に住んでいますので、卒業生の皆さん京都に来る機会がありましたら訪ねて来てください。しばらくは、大学にいたときのメールアドレスで連絡できます。


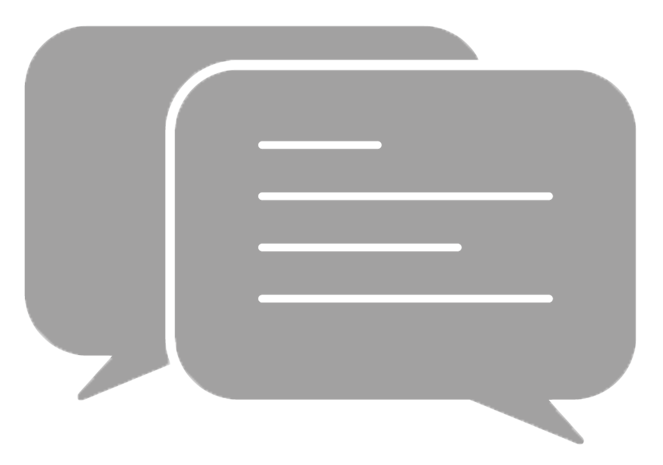 化学教室
化学教室